
第7回 京都の平熱2025
僕が小学生の頃だろうか。世にはニューアカブームが訪れ、その立役者であった浅田彰の『構造と力』(勁草書房、のち中公文庫)がバカ売れしたことを知ったのはずっと後のことだが、その「ずっと後の」時代には哲学書がベストセラーになることはなかったし、自分自身、哲学には興味があっても、文学とは違ってなかなか血肉化することができなかった。ちょっと齧っては吐き出し、多少は咀嚼ができるようになっても結局は飲み込めない。よほど相性が悪いのか。ニーチェやカントの本はいまだ我が家の本棚で埃をかぶったままでいるし、フーコーやドゥルーズは読んだかもしれないが、読んだうちに入れないほどの理解度だ。 ところが、最近は哲学書(らしきもの)を頻繁に読むようになった。これは僕の成長ではなく、たんに優秀な人が次々と現れてきたから。例えば『暇と退屈の倫理学』の國分功一郎であり『現代思想入門』(講談社現代新書)の千葉雅也だ。機転の利いた導入と手際のいい書きっぷり、程よい熱量。とりわけ前者はベスト&ロングセラーに。2011年に朝日出版社から発売されると、2015年には太田出版で増補新版が(←僕が読んだのはこれ)、そして2021年には新潮文庫に収められた。「東大・京大で最も読まれた本」は嫌らしい惹句だが、あながち見当違いの話ではない。友人のお笑い芸人(週休6日)に勧めたら僅か2日で読了してしまった。「僕もこういったことを考えていました」とは生意気な感想だが、小学生にも読めるかのような平易な語り口は天晴れである。後者はそれこそこれからロングセラーとなっていくのだろうが、何より著者自身が哲学を勉強することで人生を切り開いていった、哲学なくしては活動的生を送ることが出来なかった(と思わざるを得ない)事実が胸を打つ。読者としては合理的思考だけでなく感情的側面もフル稼働させられるのだから、もはや哲学書の域を越えている。 いや、あるいは、もう一つのベストセラー、『福岡伸一、西田哲学を読む』(池田善昭、福岡伸一著。明石書店、のち小学館新書)が示すように、異分野からの哲学理解が進んだとも。社会学と宗教学が切り離された分野ではないように(学問としては一応、別物かもしれないが)、生物学と哲学も通ずるものはある。哲学者、西田幾多郎の読解に長らく手こずっていた僕としては、この本を読み始めて十数ページ目で「アッ」と天啓に打たれた。西田の「絶対矛盾的自己同一」は言ってみれば福岡の「動的平衡」なのであり、そこを突破口として以前より遥かに西田理解が、人間理解が進んだ次第である。このような目から鱗が落ちる本が世に生み出されるには〝書く人〟もさることながら〝作る人〟(=仕掛け人)が絶対的に重要であり、内部事情は知らないが、まさか福岡が「こんな本を出したい!」と手を挙げたわけではないだろうと想像すると、ひとえに編集者の勝利、偉業と言えるかもしれない。 國分や千葉などの新鋭に先駆ける形で、現代哲学の地平を拡大してきたのが他ならぬ鷲田清一。西田幾多郎がこの世を去った4年後、1949年に京都市で生を受け、京都大学大学院を修了。フッサール、メルロ=ポンティの研究者として出発し、「身体」「他者」「モード」「皮膚」「聴く」「老い」「ケア」「所有」といった昭和の時代では見過ごされていた思索の種を〝哲学の孔〟から掘り起こしてきたパイオニアだ。もっとも、若かりし頃は「学会では温かく黙殺され」(『京都の平熱』133ページ)たと皮肉がてら振り返るようにあくまで傍流の立ち位置だったが、サントリー学芸賞を受賞した『モードの迷宮』(中央公論社、のちちくま学芸文庫)で一躍、飛躍を遂げ、今世紀に入ると、現実世界=社会との連動をエッセンスとした「臨床哲学」を打ち出し、いまや唯一無二の〝市井の〟哲学者に。彼の数え切れないほどの著作の中で我が人生に最も影響を与えたのが『京都の平熱 哲学者の都市案内』。手に取ったのは講談社学術文庫版だが、何より見た目がカッコいい。紺色の帯と表紙のモノクローム写真の相性が抜群だ。人間は顔が大事だが本も顔が命とも。余談だが、最近では『夕暮れに夜明けの歌を 文学を探しにロシアに行く』(イースト・プレス)の装丁が秀逸だった。著者の奈倉有里が何者なのかまるで知らなかったが発売日に衝動買い。しかして中味は表紙と同様の傑作であった。 「ずいぶん久しぶりの206番だ」(3ページ)と始まる『京都の平熱』は鷲田の極私的京都散策記である。この206番は京都市内で複数ある循環バスの中で走行距離が2番目に長い、1978年に廃止された路面電車=京都市電の代替輸送手段だ。洛中をすっぽりと囲む路線沿いには、東山の知恩院や平安神宮、北部の大徳寺や北野天満宮、京都駅近くの東西本願寺など数多の寺社が、あるいは、祇園を代表する京都の花街、旧遊郭、ラブホテル街が、京女、華頂、京大、ノートルダム、府立大、大谷、龍谷といった学術機関、さらには映画館や歌舞練場が立ち並ぶ。要するに、「〈聖〉と〈性〉と〈学〉と〈遊〉が入れ子になって、都市の記憶をたっぷり溜めこんでいる路線」(同書5ページ)なのだが、「そうした「表」のきわで、ひっそりとつつましくきまじめに生きてきた京都人の日常のそのただなかに、さらに「別の世界」(autre monde)につづく孔がいっぱいある」(同)ことを発見した哲学者による「裏版206番」。むろん、巷に溢れる観光ガイドの表層的、短絡的な記述はそこにはなく、これまで語られることのなかった京都人の、京都文化の真相が浮かび上がる。奇人変人が跋扈し、反骨精神に満ちた人々の躍動する町が…。 京都市内の書店でしばしば設けられてある「京都本コーナー」ではよく『京都の平熱』は最前列を陣取る。 周囲の京都本と比べると、大きさでは敵わず、色合いは地味で、ちょっと堅そうな内容っぽく、極めて劣勢な雰囲気を醸し出しているがしかし、紛れもなく第一級のベスト&ロングセラーである。昨年春、世間には「妻の長年の夢だった京都住まいを実現させたくて東京での仕事、生活に区切りをつけた」と繰り返し説明をしたものだが、本当のところは『京都の平熱』で僕自身も京都住まいへの願望が沸騰していたのだ。京都は遊ぶべき学ぶべき味わうべきものがたくさんあるのではないかと。首尾よく、何処へも行きやすい三条の手ごろな物件に出会い、娘は無事に京都の大学に受かり、引っ越しにあたって大量の本を処分せざるを得なかったことは非常に心苦しかったが、50にして新しき人生が始まったのである。この10か月間、毎日のように洛中洛外を散策し、206番沿いも随分と顔なじみとなった。京都で生まれ育った鷲田はずぶずぶの京都人だが、僕は「うぶうぶ」の京都人。時期尚早といえばそうだが、やはりやってみたいのは僕なりの「京都の平熱」。果たして、どんな孔を発見できるのか。 ではいざ出発。「きょうと206番」、京都駅から東回りで。 * * * 京都駅に降りて、まず目につくのが京都タワーだ。鷲田も再三、文中で「蝋燭」と記していたので、僕も蝋燭を模して造られたとばかり思っていたが、妻曰く「灯台」だとか。まあ、どちらも暗闇を照らす光であり、意味、機能は同じようなもの。大きな違いはない。もっとも、レトロ感たっぷりのデザインはかなり前時代的だが、いまや景観を損なう云々との文句を言う者はいないだろう。それよりもかなり年季が入ってきただけに近いうちに建て替えの必要性が出てくるに違いない。そうなったら今度はどんなデザインになるのか。そっちのほうが気になる。スカイツリーより高くなっていたりして。 このタワーのすぐ北にあるヨドバシカメラビルにはたいそうお世話になっている。我が家近くの御池通り沿いにある「ミツハシ」がスポーツ用品店の横綱だとしたら、ここの3階にある「石井スポーツ」は大関。どちらもランニングシューズ&ウエアの数は半端ない。何よりスイスのメーカー「On」の商品が大量に置いてあるのは助かる。だから外国人観光客の姿も多い。今のところは、日本よりも欧米のほうが人気はずっと高い。 東に直進し、鴨川を渡ると、すぐに三十三間堂が見えてくる。1001体の観音像で有名な仏教寺院だ。つい最近も行ってきたばかり。大的(おおまと)全国大会が行われていたのだ。いわゆる「通し矢」の競技会であり、江戸時代から続く京都正月の風物詩。今や弓は武術ではない。とはいえ、想像以上に的までの距離が長かったし(120m)、それこそ風の強い日は達者な人でも的に当てるのは難儀だろう。彼女らの(男性弓者は少なかった)真剣な眼差し、色鮮やかないでたちは一見の価値がある。晴れ着と弓の組み合わせはさながらセーラー服と機関銃だ。赤川次郎の出世作は京都にヒントがあったのかもしれない。 東山七条からは智積院を横目に北へ進路を変える。東大路通りだ。馬町という交差点を左に曲がって100mほど歩くと、左手に『三日月氷菓店』が現れる。我ら家族が京都に引っ越しをして2週間後、千葉の柏から移転してきた。ひと夏で京都市内のほとんどの有名カキ氷店を制覇した僕の感想を言えば、間違いなく№1か№2である。構成が見事なのだ。真夏でもまずは熱いほうじ茶と、しょっぱめのおかきが出される。ここで誰しもがオヤッと思う。後から隣の席に着いた若い男は「アチー」と言いながらポリポリ食べ始めていたがこれは間違い。カキ氷を食べ進めていくと、どうしたって口回りが凍えてくるし、塩気のあるものを挟みたくなる。途中で食するのが正しい。せっかちは禁物。フワっとした感触の穏やかな甘さのカキ氷は単体としても100点に近いが、脇役の有意義なアシストのおかげで120点まで上昇してしまう。ああ、おいしい。冬でも来てしまおう。 五条通を超えると、清水寺へ続く五条坂が見えてくる。昼間は平日でもごった返しているが、早朝はさすがに閑散としたもので、昨年8月には盂蘭盆(うらぼん)法話を聞きに家から走って上って参上した。午前6時開演。人類学者、山極壽一氏の共感力の話…人類には「認知革命」「農業革命」「科学革命」に先んじて「共感革命」があった、そこで果たした役割が大きかったのが音楽で、人類は実はほとんどの期間を平和的に暮らしてきた云々の話は非常に有意義であった。別に、清水寺はお金儲けがうまいだけではない。参加者にはちゃんと(?)お土産を配っていたし、安寧たる世界の構築に向けての提案はなされている。 再び東大路通りに戻り、東山安井で建仁寺方面へ左折し、そして北上すると京都WINSがある。馬券売り場だ。いっときは来場者数がかなり減ってしまったが、コロナ禍を経て、とりわけ若年層がグンと増えてきた。新宿WINSなんて、もはやアミューズメントパ-クだ。京都はというと、やや年季の入った年配者が多いか。どうして観光の中心地に場違いとも言える鉄火場が作られたのかと疑問に駆られるが、ここは地域住民の反発が少ない地域とも。僕としてはよくぞ作ってくれたとしか言いようがない。三条通り沿いにあればもっと行きやすかったが(もっとお金を減らしていたかも)、自転車置き場の近くにはうどんの名店になりつつある「麺喰金家」、あるいはすでに確固たる地位を築いた「夷川餃子」があるので昼メシには困らない。 人気の八坂神社はさらりと挨拶をする程度だけにして、その少し東北方面に構える知恩院へ。最も好きな寺である。そびえたつ三門(山門ではない)が圧倒的だ。そして石段一つ一つが尋常ではない大きさ。なぜ、こうも歩きにくい段差なのか。大男専用の道なのか。浄土宗の権力の大きさか。開宗850年…いや、851年。日本仏教の行く末はなんとも心もとないが、知恩院の迫力を目の当たりにすれば、次なる850年も安泰に思えてくるのは不思議だ。僕としては、真正面の参道からではなく、平行して走っている神宮道から近づき、木々の間からどす黒い門がヌッと現れてくる(ドキリとする)アプローチが好きである。 この知恩院から目と鼻の先、「マルシン飯店」は京都屈指の老舗中華料理屋だ。いつも行列ができている。だから店内にはなかなか入れないが、テイクアウトの生餃子を買って帰れば事足りる。このような行列店とはサラッとした付き合いがいい。もっとも、こんな出来の良い餃子は家で食べてはいけないだろう。そんな珍妙な怒りが湧いてくるほどの完璧なうまさ。決して出し惜しみをしない「マルシン飯店」の歴史は48年。次なる48年も絶対に安泰である。 さらに北へ進み、東山二条にはモダンな佇まいの「エーデルヴァイン」が異彩を放っている。なかなか手に入らないナチュラルワインがたくさん置いてあるのだから京都のワイン好きで知らない者はいまい。東京の酒店なら即座に売り切れてしまうラディコンもここならいつでも置いてある。京都の人は転売して儲けようというセコい感情が希薄なのか。これもひとえにプライドがなせるわざか。それともたんに情報収集がイマイチなのか。「エーデルヴァイン」の穏やかな経営は京都の謎の一つである。 叡山電鉄の元田中駅を過ぎて高野で左折。ここから北大路通りに入り、高野川、賀茂川を越えていく。日頃の早朝ランニングではもう少し北にある京都府立植物園辺りが折り返し地点だ。高野川のほうが風情があって好みといえばそうだが、いかんせん、走路が整っておらず膝への負担が大きい。なんでも、行きつけとなった理容室「KATO」のマスターは「鴨川も走りやすくなったのは最近ですよ」と。思いのほか、京都市の財政状況はよくないようだ。我が家のすぐ前の三条通りもボコボコが多くて歩きにくいし、昨年春まで住んでいた府中市とはゴミの収集も含めてだいぶインフラが違う。世界一級の観光都市ではあるが、お金の集め方をもっと研究したほうがいいと思うのは勝手な言い分か。 洛北高校前をまっすぐ南下すると、下鴨神社の裏側に出る。けばけばしい楼門にちょっとたじろいでしまうが、毎年、土用の丑の日の前後に行われている御手洗(みたらし)祭りには昨夏、夫婦で参加した。別名、足つけ神事。無病息災を祈願する行事だ。とにかく京都の夏はしんどい。YMCAのプール仲間のおっちゃん達も「今年の暑さは異常だなあ」と口々に言っていた。とんでもない年に引っ越してきてしまった。盆地のせいか、湿度の高さは半端ない。連日40度超えのデリーよりもよほど暑く感じる。何はともあれ、たった一日、たった数分間だけでも、冷たい水に素足を付けると心も休まる。実はこれ、北野天満宮でも8月上旬に行われている。こちらには娘を呼びつけた。平安貴族文化の勉強にも良いだろう。新鮮で楽しい時間を過ごしたおかげか、3人とも体調を崩さず無事に夏を越すことができた。 ちなみに、みたらし団子は下鴨神社が発祥の地となっているそうだが、これはもちろん眉唾ものだ。後醍醐天皇が御手洗池で水をすくったところ、最初に泡が一つ浮かび、続いて4つの泡が浮かび上がったものを団子に見立てた…との逸話が残されている。鎌倉幕府を倒したあと建武の新政の成功を祈願して下鴨神社に訪れたのは本当かもしれないが、天皇が池の水をすくうなんてことが起こり得るのだろうか。もっとも、お団子を食べながら訳知り顔で連れにこんな余話を語るのはおやつ時間を一層、楽しませてくれるものだし、歴史は作ったもん勝ちかもしれない。 じきにバスは地下にある北大路バスターミナルへ潜り込み、運転士が交代する。バスは一日中、走り続けることは可能だが、運転士は休憩が必要だ。上階には市内北部最大の商業施設=イオンモールがそびえ立ち、いっとき通ったコナミスポーツジムも入っている。この辺りが京都屈指の住宅地となっていることは鴨川ランニングでも明瞭に分かる。ホテルがわんさかと生えている三条、四条は外国人観光客のランナーが目に付くが、賀茂大橋を越えた辺りは地元民の姿が多い。犬も多い。緑はことさら多い。ここには平常な営みがある。 北大路を過ぎると、通りは南西の方向へ。全体的に碁盤の目で作られている京都市内にあって、このような斜め45度の角度で走っている道路は珍しい。北大路の〝斜め道〟は賀茂川&高野川のデルタ地帯でやや北側にしか道路を作れなかった事情だろう。 堀川通りと交差してからは、軌道修正するような形で再び西へ直進し、大徳寺を北に、船岡山公園を南に臨んだところで千本通りへと左折する。 千本北大路から徐々に坂を下って、千本上立売に到着する。ここから西に行けば北野天満宮、東に行けば「鳥岩楼」だ。このバス停の目の前には「五辻の昆布」の本店があるが、最近はあまり和食を自宅で食べなくなったのでまだお世話になっていない。「鳥岩楼」は鷲田も熱っぽく記していた鳥料理の名店である。いまは昼の営業のみ。夜の部で出されていた水炊きもたいそう美味しかったと思われるが、ここの親子丼はこれまで口にした中でも群を抜いて美味い。理由不透明の豊饒さ。だから行列が絶えない。「今日は無理だな」と入店を諦めらざるを得ないときもあるが大丈夫。すぐ近くに蕎麦屋のニューウェーブ「にこら」があるからだ。ここなら空いている(たぶん)。まだ知られざる名店である。 こちらの昼はコースのみ。店のサイトで「「今日どこで食事しようか」と考えた時にカジュアルな和食、イタリアン、フレンチ等の店と同等に思い浮かべてもらえるような蕎麦屋でありたいと思います」と宣言しているように、もはや従来の蕎麦屋の範疇を超えている。もちろん日本酒のアテとして悪くなかろうが、シャンパン、白ワインとの相性も非常にいい。繊細かつ深淵。そんな料理が並ぶ。我が家の隣にある「自在」、京都市役所近くにある「一之船入」もそうだが、いまやカテゴリーに囚われない店が俄然、増えてきた。一応は前者は和食、後者は中華だが、様々な国の料理のエキスが含まれている。10年くらい前、タイ料理の「マンゴツリー」に出くわした時も驚いたが、とどのつまりは「美味しければそれでいい」。これが正解である。 さらに真っすぐ南へ。千本中立売付近も結構、栄えており、西陣京極商店街は小さな飲み屋がしのぎを削っている。祇園の花街もそうだが、いまだに足が向かない、向いてくれない。自分の事ながら残念である。「聖」「学」「遊」は一人前とは言えないまでもそれ相応には触れてきたが、「性」だけは未来永劫、縁がないのかもしれない。 千本丸太町を過ぎれば二条駅だ。京都北路への要地。昨年末、ここから丹後へ向かった。一方、京都住まいの僕の要地はそのすぐ南を走る三条通り。それこそ「京都三条会商店街」には美味しいパン屋が複数あるし、使い勝手のよい総菜屋、スイーツ屋も。さらに我が家に向かって東へ進めば、それこそ半端ない数の飲食店があるし、プール、映画館、本屋…なんでもある。現実的に、今しばらくはここから離れられない。 さて、北大路の〝斜め道〟よりも気になるのが二条駅の少し南、千本三条から四条大宮までのそれだ。後院通(こういんどおり)と呼ばれているが、これは「明治末期の京都市三大事業の一つ(他は第二琵琶湖疎水、上下水道の整備)として行われた道路の拡張と市電の施設」のため作られた。ここまでは歴史的事実。ところが、その先が、つまり〝斜め道〟となった、ならざるを得なかった理由が不透明なのだ。僅か100年前のことなのに…。一応の説は、①千本三条の南側で幅を利かせていた材木商の反発、②住民が少ないゆえ利益確保が困難、③壬生車庫新設の問題。これまで多くの人が真相解明に尽力してきたが、今のところ決定的な資料はなく、あくまで臆説に過ぎない。まあ、解明しなければ誰かが困るというわけではないが、この〝斜め道〟を作る際、困った人がいたことは間違いあるまい。「後院通」という由緒正しいかのような名前(←これも理由不透明)をこしらえなければならなかったことも問題の深刻さを物語る。 四条大宮も足繁く通うところ。ベスト&ロングセラー的なスーパー「モリタ屋」があるからだ。ここのローストビーフも「マルシン飯店」の餃子なみの危険なうまさ。もはやローストビーフは家で食べるものである。何はともあれ、肉だけでなく他の食材、商品の質も高く、パン屋&レストラン「進々堂」と同じく京都の老舗の底力を感じる店である。 ここまで来たら、終点はもうすぐ。娘が通う龍谷大学の珍しい擬洋風建築を横目に見やり、僕が出会った〝孔〟から覗いた京都の未来に今一度、思いはせる。そこには変わらない京都があれば、変わるはずの京都もある。鷲田は「京都の住民ほど歴史意識が希薄な人種は珍しい」(『京都の平熱』47ページ)と京都人の時間感覚の欠如=京都の没歴史性を暴いて見せたが、京都人特有の〝ふてぶてしさ〟が「歴史都市」のイメージを強化、拡散するその裏側で、型破りを平然とやってのけているのではないか。京都人の二重性…僕はそんなことを今、思う。でも、まだ旅の途中だ。京都駅が目前に迫ったが、この先も乗り続ける算段である。 (図版作成:うさんぽデザイン/USA) 虎石 晃 1974年1月8日生まれ。東京都立大学卒業後は塾講師、雑誌編集を経てデイリースポーツ、東京スポーツで競馬記者を勤める。テレビ東京系列「ウイニング競馬」で15年、解説を担当。著書2冊を刊行。2024年春、四半世紀、取材に通った美浦トレーニングセンターに別れを告げ、思索巡りの拠点を京都に。趣味は読書とランニング。
東へ
北へ
西へ
南へ
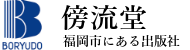


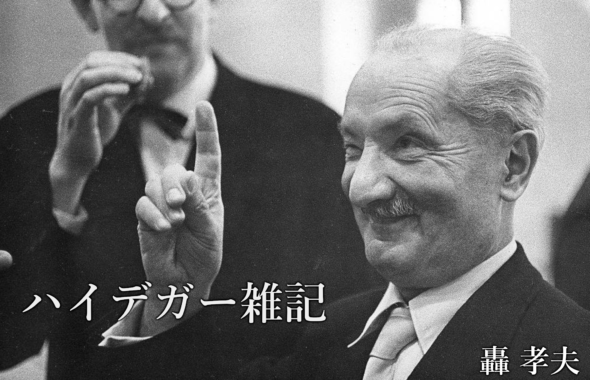

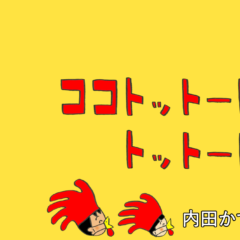

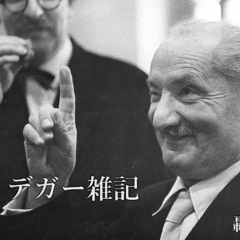
この記事へのコメントはありません。