
第6回 ヘラクレイトスの言葉を古代ギリシア語で読んでみよう
ネオ高等遊民です。今回はヘラクレイトスの古代ギリシア語を読んでみようという内容にしたいと思います。 ギリシア語が読めない人でも、ギリシア語の話の部分はざっくり読み飛ばしても分かるように書いてありますので、ぜひお付き合いください。 まずは、こんな記事を書こうと思ったいきさつから。 去年から古代ギリシア語の原典講読を本格的に始めました。きっかけは、傍流堂の連載でおなじみのクサカベクレスによるアリストテレス『形而上学』の講読セミナー(タイムヒル主催)です。あのクサカベクレスが直々にギリシア語原典講読の手ほどきをしつつ、哲学の議論ができる時間なんて、こんなに貴重な機会はありませんよね。ですから、わたくしは読書会サークルのメンバーも誘ってサークルぐるみの活動として原典講読に参加しています。 参照 市民大学「スコラタイムヒル」 = ZOOMリモート講座 = それに加えて、ネオ高等遊民読書会サークルでは、月に1度学習院大学の小島和男教授によるプラトン『エウテュプロン』原典講読も開催しています。こちらはもうすぐ読み終えて、次はもしかしたらラテン語を読むかもしれません。 そういうわけで、週に5回ほど、お昼の時間に読書会サークルで原典講読会(セミナーの予習)をしています。原典講読のためにほぼ毎日ギリシア語を読んでいる生活が1年以上続いています。 週に5回も講読を1年以上もしていると、だんだん慣れてくることもあって、たまに予習が早く終わるときがあります。そのときに、何もすることがないので、では何か別のものを読んでみようと思って取り上げたのがヘラクレイトスです。 なぜヘラクレイトスなのか。その理由は大きく言って2つ。 ①短い格言(箴言)なので、隙間時間に読みやすい ②謎めいた内容なので、原典で読むと色んなニュアンスをつかめる ヘラクレイトスといえば、ご存じの方も多いと思いますが、謎めいた格言・箴言風の言葉をたくさん残した人です。「同じ川には二度入れない」「争いは万物の父」とかですね。こういう類の文言はひとつひとつは短いので、わりと読みやすいです。 もう一つが、上記の格言のように意味が謎めいているので、たとえば「入る」って単語はほかにどういう意味があるのかとか、「争い」ってどんな単語なのかとか、そういうことを考えるのが楽しいんですね。いまある日本語訳が、これ以外に翻訳しようがない1つの正解ということがない。なので、短い原典を読むことで、ヘラクレイトスをたくさん味わってみようという意図です。 そんなことを読書会サークルでやったら、思ったよりも楽しかったので、ここにも連載として書くことで、読者の方とヘラクレイトスや古代ギリシア語を読む楽しさを共有できたらなあと思います。 ここまでが前口上です。お読みくださりありがとうございました。 ではヘラクレイトスの講読に入ります。 念のため言っておきますが、ネオ高等遊民のギリシア語力は全然大したことないので(初級文法がざっくりわかる程度)、間違ってる可能性は全然あります。何か誤りやまずい箇所に気が付いたら、どうぞご指摘をお願いいたします。 逆に言えば、初級文法がざっくり分かる程度の”語学力”でも、古代ギリシア哲学の原典講読は十分に楽しめるということをお伝えできるかと思います。 ちなみにおすすめの入門書は堀川宏『しっかり学ぶ初級古典ギリシャ語』(ベレ出版)です。 ヘラクレイトス『自然について』断片1(DK B1 = LM D1) ※DKはディールズ&クランツの断片番号(定番の断片集) LMはラクス&モストの断片番号(最新の断片集) (原典 LMベース。異読等は省略) τοῦ δὲ λόγου τοῦδ’ ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι, καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι, καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι, πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων ὅκως ἔχει. τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται. (クサカベクレス訳) ロゴス〔理〕はこの通りのものとして常にあるのだけれども、人間どもはこれを理解しない。これを聞く前も、最初にこれを聞いた後も。なぜなら、万物はロゴスにしたがって生じているのだが、彼らはそ知らぬ風だからだ。わたしが各々のものを自然にしたがって区分し、どのようであるかを示しつつ十分に物語ったそういったことばも行為も経験した者たちにしてからがそうだ。また他の人間どもは、ちょうど眠っているときにどれだけのことをしたか忘れているように、目覚めていてもどれだけのことをしているか気づいていない。 (日下部吉信編著『初期ギリシア自然哲学者断片集1』(ちくま学芸文庫)204ページより) (拙訳) このロゴスはいつもあるのだが、生じるのは理解の欠如した人間ども。それを聞く前も、はじめて聞いたときも。というのも万物はロゴスにしたがって生じているが、人間どもには無知がお似合いだから。私は自然に即してそれぞれのものを区別し、それらのあり方を示しつつ描写しているが、そういう言葉や行為について経験して(聞いて)いるにもかかわらず。だがほかの人間どもは、自分が目覚めているときにどれだけのことをしているのかに気づいていない。眠っているときにどれだけのことを忘れているのかに気づかないのと同様。 結構難しいところもあるので、困ったときはクサカベクレス訳を参照しつつ、自分でも訳してみました。 クサカベクレス訳と異なる部分を説明したいと思います。 τοῦ δὲ λόγου τοῦδ’ クサ ロゴス〔理〕はこの通りのものとして常にある ネオ このロゴスはいつもある クサカベクレスはτοῦδ’を「この通りのものとして」と副詞っぽく訳しています。 いっぽう私は「このロゴス」と、ロゴスの修飾語と理解しています。 「このロゴスって、いったいなんのこと?」と、聞く者に思わせているのではないかと考えました。 ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι クサ 人間どもはこれを理解しない。 ネオ 生じるのは理解の欠如した人間ども。 ἀξύνετοιは「理解のない」という形容詞です。LSJというギリシア語辞典には「属格を理解できない c. gen., not able to understand」という語義が記載されており、先ほどの「τοῦ λόγου」を補えば「ロゴスを理解できない」と訳すことが可能です。クサカベクレスも「人間どもはこれ(ロゴス)を理解しない」と訳しています。 ただまあそうすると、γίνονται「生じる・なる」という動詞が特に訳されておらず、ほとんど飾りになっているだけです。SVCの文型で、be動詞とほぼ変わらない感じ。ἀξύνετοιが補語です。 そこで私は、「生じる」というγίνονταιの意味を含めたいと思うので、ἀξύνετοιを補語ではなく名詞修飾語と解釈して、「理解の欠如した人間どもが生じる」とSVの文型で訳してみます。そこから ἄνθρωποι(名詞.人々、人間たち)が最後に来るように倒置して、「生じるのは理解の欠如した人間ども」です。 まとめると、「このロゴスはいつもあるのだが、生じるのは理解の欠如した人間ども。」 ἀπείροισιν ἐοίκασι クサ 彼らはそ知らぬ風だからだ ネオ 人間どもには無知がお似合いだから ἀπείροισινは形容詞で「経験がない」「不慣れな」、転じて「無知な」という意味の与格。 ἐοίκασιは動詞で「~に似ている/のようだ」「~(人)にふさわしい」という意味(~には与格)。 つまり「無知(な人間ども)にふさわしい」と訳せます。 クサカベクレスの「素知らぬ風」というのは結構意訳しているのではないかと思います。 「無知な人間どもにふさわしい」と「彼ら(人間ども)には無知がふさわしい」は厳密には違うことを言っていますが、まあ翻訳の範囲内ではないかと甘えています。 大きな違いは以上の3つかと思います。後半部分はだいぶ難しいのですが、クサカベクレスの訳はよくわかりますし、同じように訳したので省略しました。 紹介した3つの部分については、いずれもわかりやすさではクサカベクレスに軍配が上がります。 しかし、ことヘラクレイトスに関しては、意味不明に訳すほうがかえって適切なのではないかという考え方もできそうです。 というのもヘラクレイトスは格言風の言葉で語っているので、謎めいた言い方をしている箇所はあまりきれいな文章に整える必要はないし、かえって整えないほうがいいとさえ思っています。 いずれにせよ、こちらも訳文作成にあたっていろいろ工夫の余地があるというのが、ヘラクレイトス断片をギリシア語で読む楽しさです。 クサカベクレスなどの既訳を参考にしつつ、みんなでああだこうだ言いながら、自分たちでも翻訳する楽しさが伝わればいいなーと思います。 ネオ高等遊民 日本初の哲学YouTuber。タイ在住。著書『一度読んだら絶対に忘れない哲学の教科書』(2024)。ヘラクレイトス断片の読解
違いその1「このロゴス」
違いその2「生じる」
違いその3「無知がお似合い」
おわりに みんなで訳文を作るのは楽しい
YouTubeチャンネル「ネオ高等遊民:哲学マスター」:https://www.youtube.com/@neomin
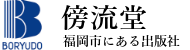





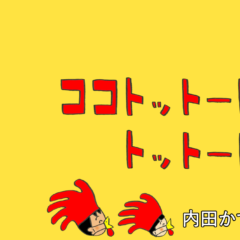

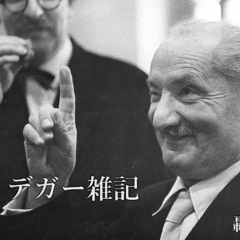
この記事へのコメントはありません。