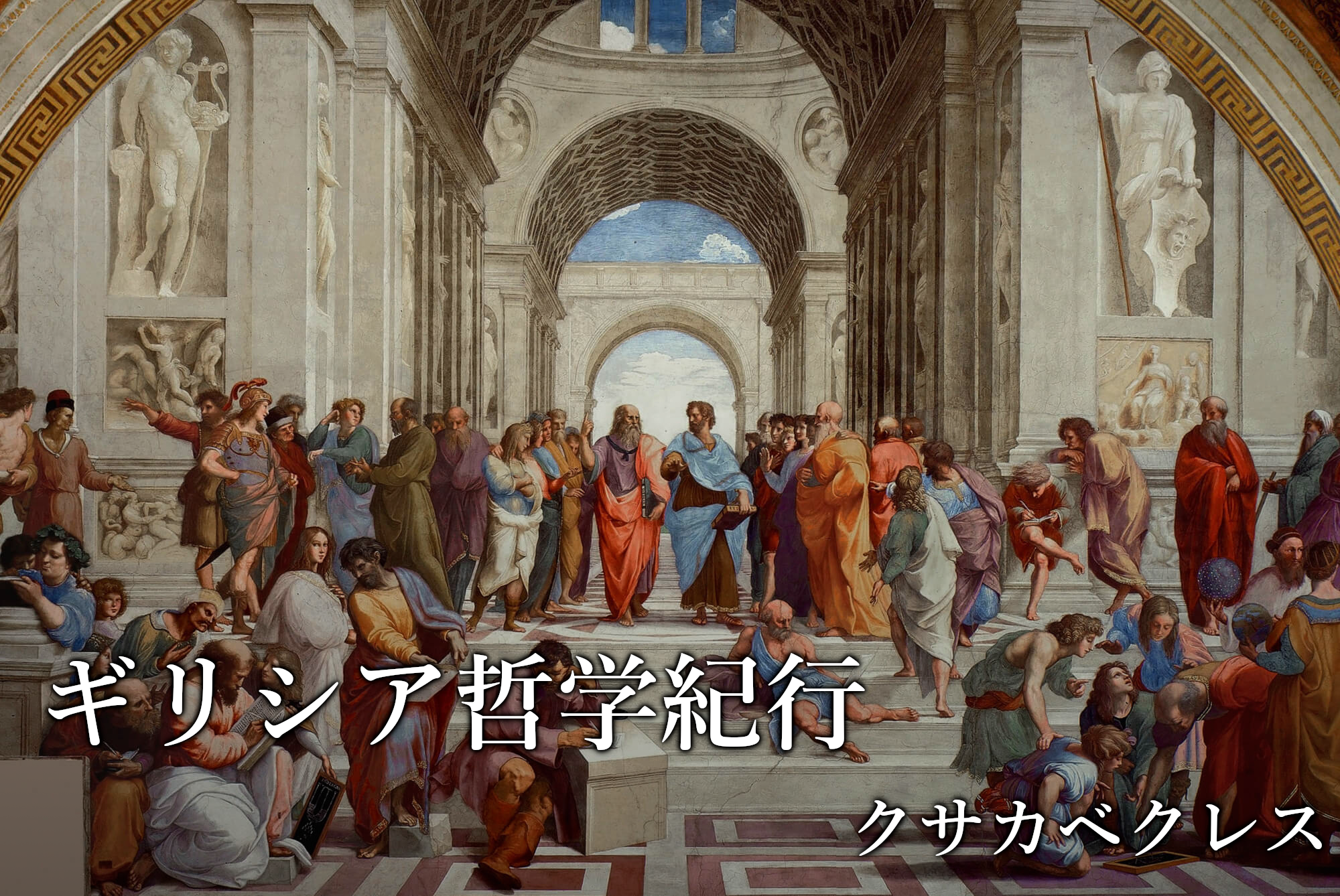
第9回 エフェソス
エフェソスはエーゲ海沿いのトルコ東岸における世界最大級の古代都市遺跡である。今日においてもアルテミス神殿跡、図書館跡、劇場跡など、数々の大規模な都市遺構が見られ、一大観光地となっている。クサダシあたりに上陸し、そこからバスで往復するというのがエーゲ海クルージングの定番コースともなっており、年間を通して観光客が絶えることはない。 いうまでもなくエフェソスは哲学者ヘラクレイトスの故郷である。 ヘラクレイトスはギリシアにおける最大級の存在(ロゴス)の哲学者であり、彼はピュタゴラスによってギリシア世界に持ち込まれた主観性原理と激しく戦った。「ピュタゴラス ― 噓つきの元祖」(断片B 81)と、ヘラクレイトスはピュタゴラスを激しく罵倒している。 ところでヘラクレイトスによればロゴスは「公的であり、共通である」(断片B2)。世界はロゴスに取り巻かれ、全体として公的なロゴスの管理のもとにあるのである。この共通の神的なロゴスを呼吸によって吸い込むことによってはじめてわれわれ人間は知的となるのである(セクストス・エンペイリコス『諸学者論駁』Ⅶ)。そのことによってしかわれわれは存在の真理につながることはできない。ところが主観性(自我意識)はこのロゴスへの通路を閉ざしてしまわずにいない。そのような主観性原理に基づく哲学が、ヘラクレイトスの洞察によれば、ピュタゴラスの哲学であり、したがってそれは存在の真理を隠蔽する哲学でしかなく、「博識、まやかしに過ぎない」のである。ヘラクレイトスが一貫してピュタゴラスとその哲学を否定しなければならなかったゆえんである。 このことは哲学に限らない。エフェソスの民衆がすでに主観性に汚染されてしまっていることをヘラクレイトスは見て取った。そのことはエフェソスの法律解釈者ヘルモドロスを追放したことに端的に現れている。そのことでヘラクレイトスはエフェソスの市民たちを激しく非難攻撃している。「エフェソスの連中は、成年に達した者はすべて首をくくって死ねばよいのだ。そしてポリスはこれを未成年の者に委ねたらよいのだ。彼らはヘルモドロスという自分たちの中で最も有為な人物を、われわれのもとには最も有為な人物などいなくてよい。そんな者がいるなら他のところで他の人たちと一緒に暮らしたらよいのだといって、追放したのだから」(『ディオゲネス・ラエルティオス』Ⅸ 2)。 ヘラクレイトスによれば、法(ノモス)は共通の神的なロゴスのポリスにおける現われに他ならないのである。それを追放するということは、まさに主観性がロゴスに立ち勝り、それをないがしろにすることに他ならず、ヘラクレイトスの到底座視しうるところでなかった。怒りと失望からヘラクレイトスはアルテミス神殿に退き、子供たちとさいころ遊びをしていたといわれる。エフェソスの市民たちが助言を求めて彼の周りに集まってきたときも、「悪党どもよ、何を怪訝な顔をしているのだ。お前たちと政治に携わるよりこうしている方がましじゃないか」ととり合わなかった(同上)。 ちなみにこのヘルモドロスという人物は、エフェソスを追放された後ローマにいたって、ローマ法の祖となったと伝承される人物である。 ヘラクレイトスの怒りと失望はこれにとどまらなかった。彼は遂には人間嫌いとなり、山中に逃れざるをえなかった。ヘラクレイトスの憤怒と失望の深さを理解しなければならない。山中の草木を食糧とする無理な生活から彼は最後には水腫を患って町に下らざるをえなくなったが、しかし医学に助けを請うことに素直になれず、あのような壮絶な最期を遂げねばならなかったのである。ディオゲネス・ラエルティオスはいう。 「彼は遂には人間嫌いになり、世間を逃れて山中で草木を食料として暮らした。しかしそのために倒れて、水腫ができたので町に下り、医者たちに謎をかけて洪水から乾燥をつくり出せるかと尋ねた。彼らがそれを理解しなかったので、自らを牛小屋に埋めた。それは牛の糞の熱で水分が発散されることを期待してである。しかし何の効果も得られず、そのようにして彼は60歳でその生涯を閉じた」(『ディオゲネス・ラエルティオス』Ⅸ 3)。 「彼は医者たちに、誰か腸を空にして液体を吐き出さすことはできないかと尋ねたとヘルミッポスはいう。それはできないと彼らが答えると、自らを太陽にさらさせ、牛の糞を塗りつけるように子供たちに命じた。そしてそのようにして長々と横たわったまま翌日死亡し、アゴラに埋葬されたという。キュジコスのネアンテスは、彼は牛の糞を取り去ることができずにそのままの状態でいて、姿が変わっていたことから彼とは気づかれず、犬の餌食になったという」(『ディオゲネス・ラエルティオス』Ⅸ 4)。 「大哲学者の死」として語るにはなんとも情けない話といわざるをえないが、このようにエフェソスはまさに「存在と主観性」という西洋形而上学の二大原理の対立がはじめて明確な形で現れた現場なのである。そしてこの対立は、西暦の初めころ、再びここエフェソスで、ヘレニズム(ギリシア精神)とヘブライズム(ユダヤ・キリスト教精神)の対立として、より鮮烈な形で生起することとなる。 円形劇場の客席に面した舞台跡のところに大きな足跡が残されている。パウロがエフェソスの市民たちと対決した跡とのことである。「十字架上で死んで三日目に蘇った方がいる」というパウロの宣教に対してエフェソスの市民たちは猛烈に反発した。ハイデガーもある講義の中で語っているが、「メガレー・テア・エフェシオーン〔エフェソス人の神は偉大なり〕」という大合唱が巻き起こり、その合唱は2時間鳴り止まなかったとのことである。足が地面にのめり込むまでパウロは踏ん張ったということであろう。これこそまさにヘレニズムとヘブライズム、存在と主観性という二大原理の対決の歴史的生起に他ならない。 エフェソスから5キロほど行った山の中腹に小さな洞がある。マリアが後年を過ごした場所であるとのことで、今日では小さな教会になっていて、ひとりの修道女が守っていた。そこがマリアの終焉の場所であることは、公式にではないが、バチカンも認めたようで、今日では巡礼の聖地になっている。 要するにエフェソスとその周辺地域は、ヘレニズムとヘブライズム、言い換えれば、存在と主観性という西洋形而上学の二大原理がはじめて近接し、厳しく対立した場所でもあるのである。この両原理の対立は、ここエフェソスから発して、この後も二千年以上にわたり、ヨーロッパ世界を抗争の中に規定していくことになる。 クサカベクレス 1946 年京都府生まれ。別名、日下部吉信。立命館大学名誉教授。1969 年立命館大学文学部哲学科卒。75 年同大学院文学研究科博士課程満期退学。87-88 年、96-97 年ケルン大学トマス研究所客員研究員。2006-07 年オックスフォード大学オリエル・カレッジ客員研究員。著書に『ギリシア哲学と主観性――初期ギリシア哲学研究』(法政大学出版、2005)、『初期ギリシア哲学講義・8 講(シリーズ・ギリシア哲学講義1)』(晃洋書房、2012)、『ギリシア哲学30講 人類の原初の思索から――「存在の故郷」を求めて』上下(明石書店、2018-19)、編訳書に『初期ギリシア自然哲学者断片集』①②③(訳、ちくま学芸文庫 2000-01)など。現在、「アリストテレス『形而上学』講読」講座を開講中(主催:タイムヒル)。
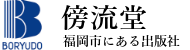

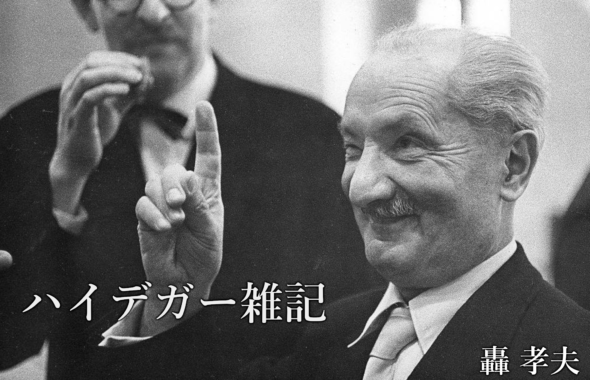



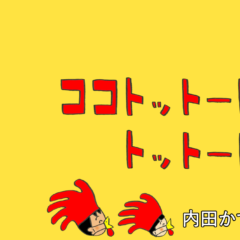

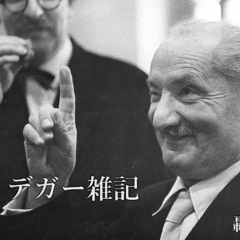
この記事へのコメントはありません。