
第9回 永遠のモダン
九つのいびつな方形が組み合わさって、一つの庭が完成されている。真如堂の「隨縁の庭」。 まだ寒さ続く3月中旬、重い足を引きずって、岡崎にある天台宗の寺院までやってきた。アンバランスながらバランスが取れており、初めて目にした光景であることに間違いはないが、初めてとは言い難い親密さもある。大きな窓の脇下に小さく置かれてあった説明書を見て納得した。 「隨縁」とは「隨縁真如」の略で、「真理が縁に従って種々の相を生じること」、つまり「真理は絶対不変でも、それが条件によってさまざまな姿を見せること」をいう仏教の言葉です。 ここまで読んで、ああ、あの小説みたいだなと思い至った。 2月の京都マラソン完走後、かねて心配していたことが現実に。いわゆる反動=筋肉痛である。下半身の各部を念入りに点検したところ、今のところは生涯続くような大きな損傷はなさそうだが、しばらくはランニングはお休みにしなければならない。朝ご飯のしたく…野菜を洗って、切って、盛り付けているだけで、両足がガクガク言い始める。ものの10分も立っていられない。主な運動はスイミングだけにとどめよう。余った時間は読書にあてればよい。そんなわけで家からほど近い大垣書店まで行ってみると、まず目に飛び込んできたのが逢坂冬馬の『ブレイクショットの軌跡』(早川書房)。彼の処女作『同志少女よ、敵を撃て』は今の今までスルーしてしまっているが、何やらこの本はかなり面白そう。そんな気配を漂わせている。早速購入して読んだところ、洗練された流暢な文体もさることながら物語の構成が見事。飲みやすいワインは正義だが、読みやすい小説もまた正義である。 同書はブレイクショットという1台の車を巡る群像劇。自動車期間工、新興ファンド会社副社長、板金工業の職人、不動産会社営業マン、中央アフリカ共和国の兵士…まるで関連性のない面々が、そして彼らの身近にいる人たちが、ブレイクショットに翻弄された時間を過ごす。善と悪、明と暗、表と裏の狭間で…。各々、いっときは苦境に立たされるが、じきに「正義」を見出すことによって再び光ある世界に戻っていく。ブレイクショットは変わらないが(→真理)、持ち主は変わり、様々な姿を見せる。いわばトリックスターたるブレイクショットによって複雑化、細分化した現代社会(投資ファンド、性差別、紛争などが蔓延している社会)があぶり出され、とはいっても悪の構造や人間関係の重要さは不変であり、ブレイクショットに関わる人たちの問題解決案もシンプル。そうして彼らはブレイクショットに出会う以前よりはマシな人生を歩んでいく。 晴れやかなフィナーレの余韻が残されているうちに再び大垣書店へ向かい、『同志少女よ、敵を撃て』を購入。善は急げだ。つい先日、佐藤優がユヴァル・ノア・ハラリの著作の中では一番面白いと言っていた『21 Lessons:21世紀の人類のための21の思考』(柴田裕之訳、河出文庫)を買いに近くの本屋を数件回ったが、どこにも置いておらずびっくり仰天。発売時期やブームが過ぎ去ると、途端に書棚から消え失せてしまうのが昨今の大手書店。それでも、まだまだ増版中の『同志少女よ、敵を撃て』は何冊も積み重ねられていた。想定通り、書きっぷりはライトノベル調ではあるが、舞台は1940年台の独ソ戦争ながらも現代社会の歪みへの怒りが通奏低音となっている。軽く読めるが、渋みや苦みがある。僕の好きなイタリアはフリウリのオレンジワインのように。これら2冊は文体も構成もまるで違うが、時折、なかば唐突に、著者の声が浮上してくるのは共通項と言えるだろう。 まずは『同志少女よ、敵を撃て』。主人公の育ての親とも言うべきイリーナが上官から「君の戦争はいつ終わる」と尋ねられ、こう答える。 自分が何を経験したのか、自分は、なぜ戦ったのか、自分は、一体何を見て何を聞き、何を思い、何をしたのか……それを、ソ連人民の鼓舞のためではなく、自らの弁護のためでもなく、ただ伝えるためだけに話すことができれば……私の戦争は終わります(122ページ) 一方の『ブレイクショットの軌跡』。瀕死の重傷を負ったエルヴェ――幼き頃、民族抵抗同盟にいわば誘拐され、一兵卒として機関銃を搭載したブレイクショットを操縦して戦場を生きる――が薄れゆく意識のさなか、突如、人生の意味に出くわす。 将来の夢――。 ジェイクに聞かれたことを、不意に思い出した。僕のやりたいこと。やりたかったこと。 僕の言葉を世界に伝えたい。僕がどんな人生を歩んできたかを、誰かに伝えたい。 それができれば、このわけのわからねえ人生も、少しは意味があるんじゃないのかな(537ページ)。 逢坂冬馬が小説を書く理由は素朴だ。そしてまた、小説家として今まさに歩き始めたとも言えるだろう。これからも僕の知らない世界の諸相を見せてほしいものである。 * * * 他方、具体的に、世界の諸相を見せてくれたのが山崎雅弘と内田樹による『動乱期を生きる』(祥伝社新書)。『ブレイクショットの軌跡』の帯には「底が抜けた社会の地獄で、あなたの夢は何ですか?」と大きな文字で書かれているが、『ブレイクショットの軌跡』は『底が抜けた国 自浄能力を失った日本は再生できるのか?』(朝日新書)を世に出した山崎へのアンサーであったか。日本がいかなる誤謬を犯し底が抜けたのか、そして今後いかなる方法で底を埋めていけばよいのか。この難問に対して全精力をかけて取り組んでいるのが戦史・紛争史研究家の山崎であり、世界の諸相に対して細緻な分析を続けている内田との対談は文字通り勉強になる。 例えば、アイデンティティポリティクスの問題。逢坂の描く独ソ戦争でも、現実のウクライナ戦争でもカテゴライズできない面々が多数存在していると思われるが、アメリカを始め日本でも「帰属すべきアイデンティティ集団を見つけて、そこに一体化すればすべての問題は解決する」(57ページ)といったイデオロギーが支配的になりつつあると内田は警鐘を鳴らす。本来は、すべてのアイデンティティ集団のひとつ上のレベルに、いかなるアイデンティティ集団にも帰属しない中立的な判断基準があるという考え方があるのに。LGBTは最近ではLGBTTQQIAAPまで細分化=集団数が増加しているというが、人間のセクシュアリティはアナログの連続体だけに原理的には全人口まで細分化し得るものであり、無理やりカテゴライズしていくことにどんな意味があるというのか。「敵と味方の間に線を引いて、その勝敗だけが問題になる」(『動乱期を生きる』58ページ)世界はレイシズムを助長し、人々を思考停止状態に陥らせる。 格差拡大、分断の問題に関して内田が投げたボールに、山崎はこう打ち返す。 「人間を属性によって分類し、自分と同じ陣営か否かで発言への評価を変えるというのは、知性でなく打算に基づく思考法だと思います~敵か味方かという陣営思考で発言の内容と発言者の属性をリンクさせる態度は、論理的な反証をせずに発言の信憑性を貶めることを意図した、卑怯な行為です」(『動乱期を生きる』62ページ) このあとは「粗雑で攻撃的な態度が広まっている背景には、議論の場としてのインターネットの特性があるようにも思います」と続き、人間の卑しさを肥大化させるネット=SNSの歴史的功罪、国家レベルにおける倫理面の低下を指摘していく。「ナチスの例を挙げるまでもなく、社会の底が抜けて国家が粗暴な方向へと走り出した」(同書69ページ)との結論はおそらく正しかろう。いずれにせよ、世界の諸相を俯瞰に眺めると同時に、細部にも目を凝らし、過去への眼差しは容赦ないが、その分、未来への射程は遠くとる。好敵手による緊迫感溢れる応酬であった。 * * * この冬出会った、もう一つの実りある対談書だったのが、奥泉光と原武史による『天皇問答』(河出新書)。戦前戦中体制の中心にいながら敗戦後も相変わらず我が国の中心的存在(≒象徴)であり続けている天皇の存在が「不自然」と感じる奥泉が政治学者の原に様々な質問を投げかけながら、今後の天皇制のあり方、あるいは天皇制撤廃後のあり方を探っていく。大正天皇の皇后=貞明皇后の宮中儀礼に対する熱心さ、二・二六事件の真相、平成天皇皇后への強烈なバッシングなど巷説、異聞といった挿話にも事欠かないが、「仮にこのまま男系を続けようとするのであれば、悠仁親王が結婚し、相手の女性が男子を産むしかない。先ほど女性に負担がかかると言いましたが、女性天皇・女系天皇を認めたとしても絶対に子どもは産まなければいけない。皇室の女性に子どもを産まない自由はないのです。その負担はまったく軽減されないわけで、そういう意味でも、多様性やLGBTQを認めていこうという時代とまったく乖離している」(『天皇問答』197ページ)という原の指摘には意表を突かれた。当たり前といえば当たり前の話なのに。さて、我が国で長らく続いてきた天皇制のあり方が大きく変貌したのは明治維新だ。 奥泉 東京に移っただけではなくて、それまでの女官たちもクビにしているんですよね。 原 はい。旧来の典侍以下三六名の女官をクビにしています。 奥泉 それから、宮中行事の仏教的なものはやめる。逆に神道的な宮中行事を新規に導入する。大嘗祭、新嘗祭などは以前から続いていたけれども、それ以外の新しい行事はすべてこのときにつくられたという話は前にしましたが、改めて確認しておきたいところです。 原 そうです。 奥泉 「古い」伝統の新たな創設。それは京都から東京に移る断絶のなかで起こった。 原 重要なご指摘です。しかも、京都から東京に移ってきたことで天皇自身も男性化するわけです。外見的にも、京都にいたときは中性的な格好をしていた。 奥泉 お歯黒もしていたのですよね。 原 そうです。いわば柔弱な天皇だったわけです。京都から東京に来て江戸城に入るということは、天皇自身も男性化し軍事的なシンボルになるということを意味する。そこも非常に重要なポイントではないでしょうか。(『天皇問答』93ページ) じきに「万世一系」のイデオロギーがつくられ、熱心に日本各地を行幸し、明治になって新たに創作された宮中祭祀も欠かさず(後半期の明治天皇は代拝が多かった)、日清戦争、日露戦争を経て、全国的に天皇崇拝が浸透し、いっとき天皇機関説が沸騰したものの(昭和天皇自身は「機関で良いのでは」と言っていたそうだが)、大規模な奉迎の場における万歳や君が代を使ったイメージ戦略で一層、権威を高めていく。そうして太平洋戦争の頃には奥泉が言う「大衆の熱狂」が完成に至った。ポツダム宣言を受託してなお、敗戦確定ながらも神功皇后をまつる福岡県の香椎宮に勅使を参向させて「敵国撃破」を祈らせたという異常性もその一つの現れ。が、戦後、天皇は退位、謝罪せず、一方の国民も、不思議なことに、天皇を熱狂的に受け入れた。ここで取り残されたのは「正しくはない戦争」で死んでいった軍人、軍属たち。そんな行き場を失った死者の声を呼び起こしたのが、奥泉の小説『虚史のリズム』(集英社)だ。娯楽的要素をたっぷりと詰め込まれた重層的な歴史ミステリーだが、腱鞘炎を起こしてしまうほどの重量だけに、多くの読者の手に届いたのかどうか不安である。 逆に、たやすく手に取ってしまえるのが伊勢谷武『アマテラスの暗号』(宝島社文庫)。出張先の新橋の本屋で、新幹線内で読むのに適した本を探して見つけた小説だ。単行本が発売された2020年、そして翌年も一世を風靡したのは覚えている。本の帯にある「『ダ・ヴィンチ・コード』を凌ぐ衝撃の名著!!」が本当かどうかは不透明だが、遅ればせながら同書との縁を獲得した次第である。 ゴールドマンサックス元トレーダーのアメリカ在住日本人が父の死をきっかけにして帰国し、秘められた自身の、そして我が国の歴史を掘り起こしていく。日ユ同祖論、アマテラス神話の更新が二大テーマ。カタカナとヘブライ語の相似から始まって、千葉県芝山町から出土したユダヤ人さながらの埴輪、広隆寺に伝わる「十善戒」とモーゼの「十戎」の類似、中東のタペストリーを吊るした祇園祭の山鉾(ギオン「GION」祭りとは古代ユダヤのシオン「ZION」祭りが由来?)…豊富な写真と図がリアリティーを増し、興味をさらに掻き立てる。小説にあるまじき手法とはいえ、そもそも著者自身、あとがきで「本書のテーマである古代史、神話、宗教は比較的人を選ぶテーマですが、このような想いから、ノンフィクションとしては出版しづらい内容という理由以上に、幅広い層の人に読んで貰いたいという理由のために小説形式で著しました」と説明しているように、人物描写、ストーリー展開、そして文体は二の次。お世辞にも優れた小説とは言えないが、優れた読み物だ。あるいは、紀行文やガイドブックとしても十分に楽しめるかもしれない。諏訪大社、木嶋坐天照御魂神社(京都府)、磐境神明神社(徳島県)、出雲大社、大神神社、大和神社、石上神宮…実にたくさんの、そして興味深い神社を主人公が訪れていく。僕もいずれは、と強く思う。 * * * 優れた小説に出会った。松家仁之の『沈むフランシス』(新潮文庫)。処女作の「火山のふもとで」の文庫化が今年1月。これ幸いとし、京都市役所の地下街にあるふたば書房の棚からヒョイと取り上げたところ…久々に読むことの愉悦を覚えた。出会えて良かった。松家は長らく編集者として活動してきたようで、本格デビューは50歳を過ぎてから(大学生時代、文芸誌に投稿歴あり)。作品を生み出していくごとに変化、成長(あるいは劣化)していく大多数の作家と違い、最初から完璧、完成されている(と思う)。すでに大作家である。我が大学時代、リチャード・パワーズの『舞踏会へ向かう3人の農夫』(河出文庫)を読んだときの衝撃に近い。 松家の言葉は美しい。だからすべてが美しい。チリ一つ落ちていない延暦寺の浄土院かのよう。だから絶対に2作目も秀作だと確信して読み始めたが、またしても舞台が素晴らしくいい。浅野山のふもとを吹き渡る青々しい風も心地よかったが、道東の寄る辺のないひんやりとした風も身に染みる。『火山のふもとで』と同じく、ノスタルジーの一歩手前で踏みとどまっているせいか、沈鬱なシーンになってもどことなく明るい。齟齬、不穏、そして陰口までもが、目も眩むようなタスペトリーを織るためのアイテムに過ぎず、読み終えてもなお、風のように、ずっと先まで物語が続いていくかのような…。 松家の作品はまさに「永遠のモダン」。これは、枯山水の石庭は決して古いものではない、永遠不変のものだと高らかに宣言した庭園家、重森三玲の言葉だ。昭和の時代、東福寺方丈庭園、松尾大社庭園、大徳寺山内瑞峯院など約200もの斬新な庭園を築き、そして2010年、孫の千青が型破りな「隨縁の庭」を完成させた。真如堂と縁深い三井家の家紋を題材とした見事なパッチワーク。不変で普遍の美が、ここにもあった。 虎石 晃 1974年1月8日生まれ。東京都立大学卒業後は塾講師、雑誌編集を経てデイリースポーツ、東京スポーツで競馬記者を勤める。テレビ東京系列「ウイニング競馬」で15年、解説を担当。著書2冊を刊行。2024年春、四半世紀、取材に通った美浦トレーニングセンターに別れを告げ、思索巡りの拠点を京都に。趣味は読書とランニング。
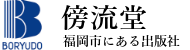




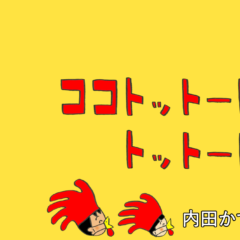

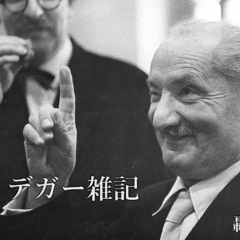
この記事へのコメントはありません。