
第3回 倭国大乱と邪馬台国の誕生
第1回で示した倭国大乱を経て邪馬台国が誕生する経過を示した魏志倭人伝を再掲します。 【 倭国は初め男王が治めていたが住むこと70〜80年を経て倭国大乱が起こり相攻伐して年を経る。共に一女子を立てて王とした。女王卑弥呼は年が長大で鬼道に仕え、夫はおらず男弟が補佐している。邪馬台国は宮室、楼観(見張台)、城柵があり守備兵がいる。民は租賦(租税)を納める。邪馬台国の兵器は矛、楯、木弓、鉄の鏃(矢じり)などである。養蚕をして絹織物を紡いでいる。】 倭国大乱が何年頃起こったのか、倭国とは日本のどの地方までを指すのか、倭国のうちどの国が敗れて邪馬台国が誕生したのか、魏志倭人伝だけでは良く解りません。そこで、范曄(はんよう)が記した「後漢書」と、姚思廉(ようしれん)が記した「梁書」、張楚金(ちょうそきん)が記した「翰苑(かんえん)」にもこの頃の倭国のことが書かれているのでこれらを援用します。 【 後漢書:建武中元二年(57年)倭の奴国(なこく)が後漢に貢物を奉げた。返礼として光武帝は奴国に印綬を与えた。安帝の永初元年(107年)倭国王の帥升(すいしょう)等は使役人160人を献じ、謁見することを願う。桓帝と霊帝の間(146~189年)倭国大いに乱れ数年間、王がいなかった。一女子あり名を卑弥呼と言う。年長ずるも嫁(か)せず、鬼神の道に仕えて良く妖をもって衆を惑わす。倭国は共に立てて王となす。 】 【 梁 書:後漢の光和(178~184年)に倭国乱れ、相攻伐して年を経る 】 【 翰 苑:中元の際に紫綬の栄】 後漢書によれば奴国は57年に光武帝から印綬を授けられました。印とは印鑑のことで、綬とは印鑑に付ける組紐(くみひも)のことです。翰苑によれば組紐の色は紫で、印に紫の組紐が付くのは金印と決められているので、光武帝から授けられたのは金印紫綬とわかります。すなわちこれが江戸時代の天明4年(1784年)に現在の福岡市の志賀島の叶崎(かのうざき)で農作業中の甚兵衛が掘り当てた「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」金印であることは間違いありません。「委」は「倭」の簡略文字として代用されました。金印は蛇鈕(だちゅう)という蛇のつまみが付いています。古代中国が諸民族に授けた印鑑は朱肉を付けて押印するためのものではなく、封書などの口を粘土で閉じて(「封泥(ふうでい)」といいます)その粘土に押印するためのものです。粘土は固まって開けると壊れるため、受取人本人しか開けられない機密性を保証する仕組みです。 奴国の金印については、福岡藩の儒学者である亀井南冥(かめいなんめい:1743~1814年)が偽造したものだという説が出ました。歴代の漢民族が周辺国へ授けた印の鈕には亀、虎、駱駝、羊はありましたが、蛇が付くのは奴国の金印が唯一であったため怪しまれたのです。しかし、現在では本物であることが証明されています。その証拠は、金印の一辺が2.3cm四方あり、江戸時代には知られていなかった後漢の1寸に正確に一致したのです。決定的だったのは、1957年に中国雲南省から一辺の大きさが同じく後漢の1寸の蛇鈕金印である「滇王之印(てんおうのいん)」が新たに見つかったことです。蛇紐であることが本物の証拠になった劇的瞬間です。蛇紐金印は福岡市博物館で常設展示されており(他館への貸出しのため2025年4月24日~5月8日はレプリカを展示)、私も十数年前に四方八方からじっくりと拝見しました。金印の蛇は見返り美人のように後ろを振り向いています。九州の別の博物館では蛇紐金印のレプリカを展示している所もありますが、本物の蛇の鱗は彫りが深く正に国宝に相応しい威光を放っています。 さて、奴国が次に後漢へ貢ぎ物をしたのは金印をもらってからちょうど50年後の107年です。倭国王の帥升「等」と書かれていて、あたかも倭国王が複数いたかのようです。このころ既に奴国の衰退の兆候を反映しているのかも知れません。しかも、後漢の皇帝に謁見できたのか、返礼品をもらえたのかが書いてありません。この頃は後漢でも国内が乱れ始めており、奴国の衰退は後ろ楯になっていた後漢の衰退とパラレルになっているように思えます。いずれにしても、後漢書の記述や金印の存在により、倭国大乱の一つの勢力は福岡平野の奴国(連合)で間違いありません。そしてもう一方は大きな人口を持ち新たに力を付けてきた筑紫平野の後の邪馬台国(連合)です。梁書によれば倭国大乱は光和(178~184年)に行われたので、邪馬台国誕生の実年代は180年代と考えられます。奴国と邪馬台国の戦争や金印が志賀島に埋められた事情については安本美典氏の『奴国の滅亡』(毎日新聞社)が秀逸です。ただし、この時の奴国王は亡くなったかも知れませんが、奴国はその後も邪馬台国の属国として存続したことが魏志倭人伝から読み取れます。 「倭国の男王が住むこと70〜80年を経て倭国大乱が起こった」と書いてあります。倭国大乱の年代を計算しやすいように単純化して180年とすると、その前の70〜80年前は100~110年の帥升の時代に当たります。しかしその50年前に奴国は金印をもらっていて、奴国が誕生していきなり後漢に朝貢できないと思うので、奴国はさらに助走期間があったはずです。つまり、奴国時代は150~200年(=80+50+α)くらい続いたと思われます。ではなぜ「住むこと70~80年」と書いてあるのでしょうか。それは奴国には須玖岡本(すぐおかもと)遺跡、安徳台遺跡、比恵那珂遺跡、西新町(にしじんまち)遺跡など宮室の候補になる遺跡がたくさんあり、奴国内で何回か都を移した可能性があります。王の代替わりなどに遷都する習慣は、その後の邪馬台国時代にも大和朝廷時代にも見られ、引き継がれて伝統になっているように思えます。すなわち、70~80年は帥升時代だけの継続期間と見ることができそうです。 一方、邪馬台国奈良説では倭国大乱をどのように考えているのでしょうか。奈良説では戦いの相手は西から奈良へ攻め入ってきた九州勢力と漠然と考えているようです。北部九州説では明確だった奴国の「な」の字も無く曖昧になっています。倭国大乱の証拠として、九州から瀬戸内海沿岸を経て奈良まで広がる高地性集落の分布を挙げています。高地性集落とは見晴らしの良い小高い丘にある守備兵の居住地で、見張り台やのろし台などがある防御集落です。高地性集落は紀元前から西日本を中心に作られ始め、消長を繰り返しながら大和朝廷が誕生する頃まで作られ続けます。もちろん、奈良説では、奈良勢力が勝利して纏向に邪馬台国が誕生したことにしているのです。その後の邪馬台国は九州の伊都国に一大率を派遣しましたが、その伊都国の様子には興味が無い一方で、奈良の高地性集落の様子は微に入り細に入り分析して、奈良のことばかりを深堀りするのです。「敵を知り己を知れば百戦危うからず」と言いますが、奈良説を唱える考古学者は敵国や後の伊都国などの属国には興味がないようです。 しかし、奈良説は敵国や属国を軽視した結果、倭国大乱の筋書きに決定的な過ちを犯しているのです。魏志倭人伝にははっきりと「倭国は初め男王が治めていたが住むこと70〜80年を経て倭国大乱が起こり、数年後に卑弥呼を女王とする邪馬台国が誕生して終結した」旨が書かれています。魏志倭人伝のこの部分を慎重に読み解くと、倭国大乱の前は長年に渡り「倭国の全体」を男王が治めていましたが、倭国大乱の結果、男王は負けてしまい女王卑弥呼の邪馬台国が勝ったと書かれているのです。つまり倭国大乱とは倭国「内乱」なのです。これを奈良説に適用すると、倭国大乱の前の倭国は九州勢力と奈良勢力とで構成されていて、九州勢力の男王、つまり奴国王が奈良勢力も支配下に置いて長年に渡り治めていましたが、内乱が起きて奈良勢力の女王卑弥呼が勝ちました、という筋書きになってしまうのです。しかし長年に渡り奈良勢力は奴国王の支配下に置かれていたなんて、奈良説を唱える学者が認めるはずがありませんし、これまで一度たりともそういう発想をしてこなかったと思います。奈良は初めから最後まで、とにかくスゴイのだという先入観を持ったことにより、倭国大乱が倭国「内乱」であることを見逃して墓穴を掘ってしまったのです。奈良がスゴクなるのは280年頃に大和朝廷が誕生してからのことです。 奈良説の学者が説明している高地性集落については、180年ごろに終結した倭国大乱より約100年後の遺構なので後々の回でお話しします。今回、邪馬台国と卑弥呼の政治体制へと進める予定でしたが、意外と手間取ってしまいましたので次回にお話しします。 高橋 永寿(たかはし えいじゅ) 1953年群馬県前橋市生まれ。東京都在住。気象大学校卒業後、日本各地の気象台や気象衛星センターなどに勤務。2004年4月から2年間は福岡管区気象台予報課長。休日には対馬や壱岐を含め、九州各地の邪馬台国時代の遺跡を巡った。2005年3月20日には福岡県西方沖地震に遭遇。2014年甲府地方気象台長で定年退職。邪馬台国の会会員。梓書院の『季刊邪馬台国』87号、89号などに「私の邪馬台国論」掲載。
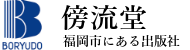




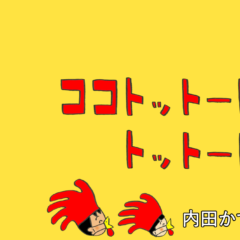

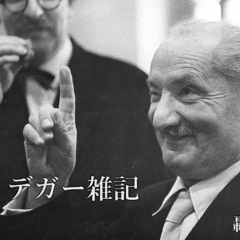
この記事へのコメントはありません。