
第1回 哲学は生き方だという哲学史を書いてしまいました
ネオ高等遊民です。2024年4月に『一度読んだら絶対に忘れない哲学の教科書』(以下、『ネオ哲学史』)という本が出版されました。古代から現代までの哲学の歴史をコンパクトに解説した本です。わかりやすくて深い内容をもった本になるよう目指しました。 『一度読んだら絶対に忘れない哲学の教科書』(SBクリエイティブ)は全国書店、ネット書店にて大好評発売中! 『ネオ哲学史』で私は哲学を「生き方」と強く結びついた学問であることを強調しています。よく知られている通り、哲学(philosophy)という言葉はもともと「知を愛する」という意味であり、人のあり方を示していると言えます。特に古代ギリシアでは、哲学者の優れた(変わった)生き方が逸話としてたくさん残っています。 近代以降の哲学は学的側面・職業的側面が強くなっていき、生き方という側面は古代よりは薄れていきました。とはいえ、いまだに哲学や哲学者には、なんらか優れた生き方やあり方を期待されてもいますし、現代の私たちが哲学を学ぶきっかけも、「人生について考えたいから」といったような理由がいまだに多いはずです。 そのような事情を踏まえつつ、哲学の歴史を語る上で、『ネオ哲学史』が「哲学とは生き方である」という見解を掲げたことの意味を説明します。この説明によって、哲学の歴史についての理解が深まれば幸いです。 知は生き方を変える力を持つ 『ネオ哲学史』で哲学が生き方であるということが特に強調されている箇所は、最初に出てくるタレスとピュタゴラスです。こちらの2人については、版元のSBクリエイティブが提供する「試し読み」で無料で読める範囲ですので、書籍をお持ちでない方も、ご覧くださると嬉しいです。 一言でポイントを述べれば、タレスが最初の哲学者と言われる理由は、新たな生き方を始めたからだと解説しました。逸話が伝えるタレスの生き方とは、井戸に入って天体観測をしたり、船の上で星を見つめたり、お金儲けの才能があるけどそんなことには興味をもたないような生き方です。 また、ピュタゴラスは、自然と数との美的調和という思想の持ち主です。この思想は、感覚からできるだけ離れ、知性を磨く生き方を導きます。これが「魂の浄化」や「肉体は魂の墓場である」という言葉が持つ哲学的意義だと解説しました。このような「ピュタゴラス的生き方」と呼ばれた生活は、プラトンおよびプラトニズムにほとんどそのまま継承されています。 同じことを少し別の角度から言い直してみます。古くは哲学とは実在がなんであるか、現実とはなんであるか、真なる認識とはどんなものであるか、といったことを問うていました。そのような問いから帰結されることによって、人の価値観や世界の見え方が変わるのは、ある意味では当然でしょう。たとえばデモクリトスのように、決して観測できない原子と空虚が実在であり、私たちの目の前に現れる諸現象は思惑にすぎないと考えるならば、いちいち目の前のことに夢中になったり信じ込んだりするのは愚かなこととなるわけです。そこでデモクリトスの場合には、せいぜい「快活さ」といったものが生活上での望ましい徳だろうと帰結します。 このような哲学者たちの思想やあり方は、知が人間の生き方を変える力を持っていることを示すものです。古代では、みずからの哲学的見解と生き方が一致することが当然であるかのように考えられていたと思われます。 つまり、哲学とは、私たちの実際の生き方とまるで無関係な知を扱う学問ではありません。それを本当に納得したならば、自分の生き方が変わらざるを得ないような知を扱う学問です。少なくとも原点においては、哲学とはそのような学であったことを、ネオ高等遊民は改めて強調したかったのです。 「昔はそうだったかもしれないけど、現代でそんな話を振り回すのは時代遅れだよ」という考えも、もちろんあるでしょう。とはいえ、哲学における知とは、よく揶揄されるように単なる言葉遊びだったり、頭の中だけのゲーム(知的遊戯)などでは決してありません。哲学とは、その人の生き方となんらかの意味で関わらざるを得ないような知だというのが、ネオ高等遊民の考えです。 以上の話から言えることは、知は私たちが扱う対象にとどまらず、私たちのあり方・生き方を規定する力があるということです。知とは使いこなすべきツールという側面がありますし、しばしば強調されるのはそういう側面なのですが、それは一面的なものでしかありません。むしろ、知のほうが私たちを規定するという側面こそ重要であり、強調されるべきことです。 言い換えれば、知には強制力があるということです。たとえばプラトンが描く哲学対話にしても、人々が対話相手(ソクラテス)に対して同意するのは己のプライドが許せないが、語られている事柄に対しては同意せざるを得ない、という状況がみられます(『国家』『ゴルギアス』など)。そういう時はたいがい沈黙したり、対話からの離脱を試みたりするのであって、知や対話そのものの無効を宣言することはできません。 このことが示すのは、知は私たちを超えた力を持っているということです。ソクラテス風に言えば、哲学対話には、私たちが知を吟味するだけではなく、知が私たちを吟味するという側面が確かにあるということです。哲学が生き方であるという話を強調するのは、知が私たちを吟味するというこの点に、より光を当てるという意図があります。 私たちはともすれば哲学なりなんなりを役立てるとか、哲学を使いこなすという動機を持ちがちですが、哲学は私たちに大人しく使われているだけの知ではないということも、語られてよいでしょう。 いくらか抽象的な言葉遣いなので、ここでネオ高等遊民自身を例にとって、具体的な話をします。ネオは、役立つ哲学といったテーマを語ることが苦手です。いわば「実用」という尺度で哲学を語ることと言えます。そういう話は需要があるし、ウケもいいですから、できるに越したことはありません。これが得意だったらもっとYouTubeも人気出るだろうなと思います。でも、なかなかできませんし、あんまり積極的にやりたいとも思えません。 その理由は別に「哲学とはそもそも役に立つ学問じゃない」とか「そのような実用的な動機はけしからん」とか、よくある上から目線の衒学的ポジションを確保したいからではありません。そんな口だけのことなら誰でも言えますから。そういうことをいう人に対しては「では役立つという動機で哲学を学ぼうとすることが恥ずかしく思えるような素晴らしい話を、どうかしてみてくれませんか」と思います。それこそ行動や生き方が変わるような話を、です。 いっぽう、私の場合は、なんと言いますか、「哲学は自分より上にある」というような感覚を持っているのです。私が哲学を判定・評価するのではなく、哲学が私を判定・評価するのだという感覚です。評価・判定されるべき自分が、哲学を特定の尺度で判定しようとしても、自分の器や尺度に応じたスケールの小さい話にしかならないだろうと感じています。 そういうふうにならないためには、過去の哲学や哲学者たちを、できるだけ彼ら自身の言葉に即して理解しなければなりません。これがまず哲学を理解する上での最低限の態度でしょうし、ほとんどの哲学の解説書がやっていることです。 しかし同時に、単なる事実の記述に終始してもなりません。それでは哲学ではなく、ただの記録・文書です。自分にとって重要性や意義を感じられるような理解が必要です。ここが自分自身の器やあり方が試される場所です。自分はどんなことに関心をもち、何を重要だと考えているのか。それは心からそう確信しているのか、それとも単に言葉や理屈をあてはめてみただけなのか。そういう自分のあり方すべてが問われることになります。 哲学の歴史を書くこと、哲学の解説めいたものを書くことは、過去の哲学を評価・判定することにほかなりません。一定の判断を下さざるを得ません。デカルトの何がすごいのか、コギトの何がすごいのか、そういうことを説明しなければならないわけですが、それぞれの哲学や哲学者に対する説明や評価が、まさに自分自身のあり方や器を表すことになります。 今回の『一度読んだら絶対に忘れない哲学の教科書』の記述も、まさにネオ高等遊民のあり方や器がありありと現れているはずです。哲学を学び、理解を試みようとする以上、自分自身のあり方と向き合わざるを得ない。したがって、哲学とは生き方とは切っても切り離せないし、哲学史でさえもまた、それを学ぶ者のあり方が現れる場所です。 そのような考えのもと、『ネオ哲学史』では「哲学とは生き方である」という、古代ギリシア的な哲学の姿を重視しました。 ネオ高等遊民 日本初の哲学YouTuber。タイ在住。著書『一度読んだら絶対に忘れない哲学の教科書』(2024)。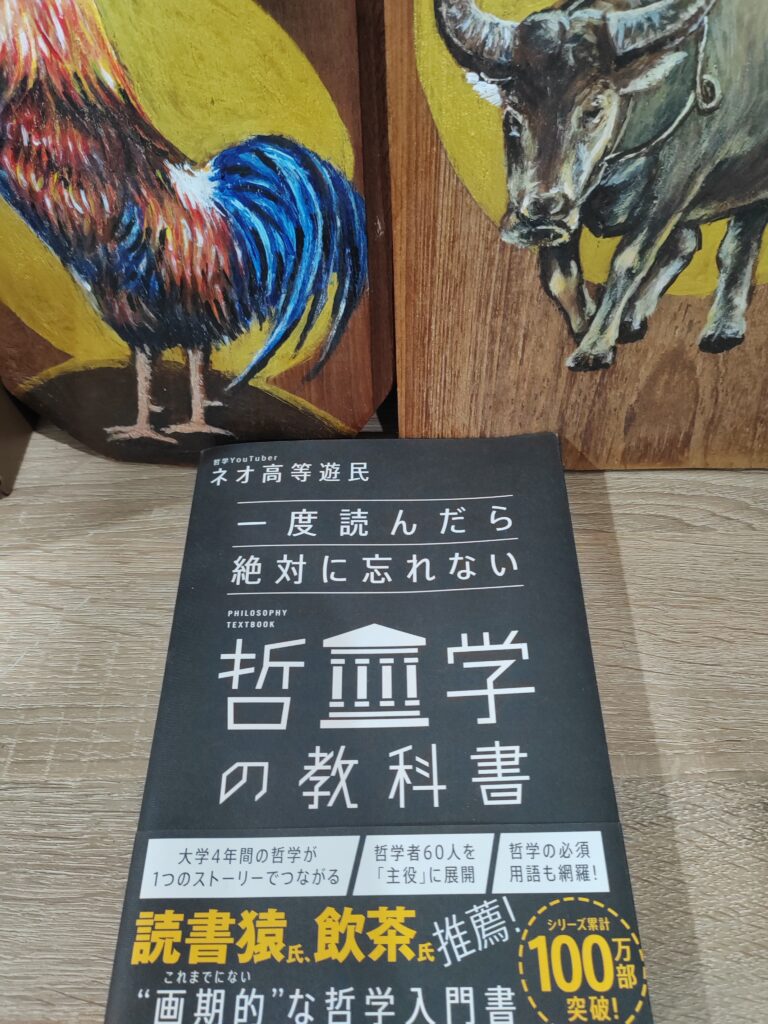
私たちが知を判定するのではなく、知が私たちを判定する
YouTubeチャンネル「ネオ高等遊民:哲学マスター」:https://www.youtube.com/@neomin








この記事へのコメントはありません。