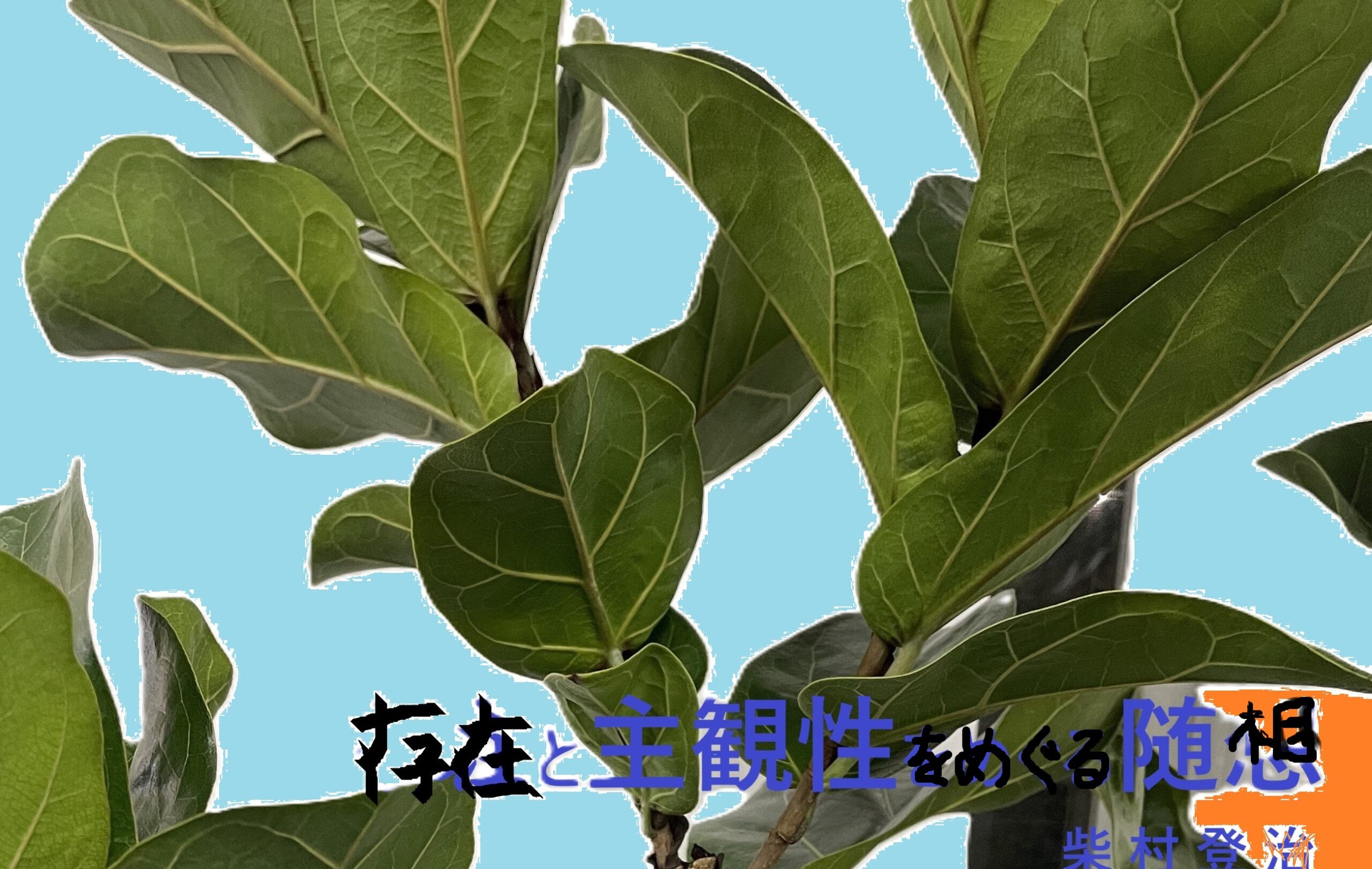
第2回 かつて詩人だった
僕はかつて詩人だった。20代の終わりから30代の終わりにかけて、僕は多くの詩を書いた。数えたことはないけれども、紙の切れ端に書いたもの、未完成だったもの、ボツにしたものなどをぜんぶ合わせたら、もしかしたら千くらいはあったかもしれない。 そのころ僕は、組織に属したこともあったし、属さずフリーだったこともあった。日雇いの労働者だった時期もあったし、給料をもらう仕事は何もしていないという時期もあった。付き合っている人がいたこともあったし、いないこともあった。髪を赤茶色や金に近い色に染めたこともあったし、染めずに伸ばすだけのときもあった。公的な場で発言することもあったし、誰かとことばを交わすということがまったくない日もあった。 詩を書いていることを、僕は誰にも話さなかった。そのことを誰にも知られたくなかった。というより、誰かに知られてはいけないと思っていた。(「詩を書く」ということはそのころの僕にとって、ほかのどんなことよりもたいせつなことだった。) だから当時、僕が詩を書いていることを知っていた人は本当にこの世界に一人もいない。同僚はもちろん、友人、恋人、家族の誰にも、僕はそのことを話さなかったから。 組織に属していたとき、その構成員が集まる建物(ビル)の一室にいながら、仕事をしているふりをして(仕事している風を装って)、詩のことを考えていたことも少なくないのだけれども、なすべき仕事はきっちりこなしていた(成績もよかったし、組織の中でそれなりにうまく立ち回った)ので、誰からも気づかれたり疑いをもたれたりしたことはなかったし、実際に職場の人から何かを言われたことも一度もなかった。表に出さず考えることを規制することまでは誰にもできない。そうやって密かに考える行為そのものが、というより、密かに書き、自分が書いたものが誰にも決して読まれることがない、という事実こそが、僕にとって詩のようなものだったと言えるかもしれない。 詩を書いていることを何年ものながいあいだ黙っていることは、つらいことでも苦しいことでもなんでもなく、いとも簡単に実行できることだった。ふつうの世間話にはそれなりに周りに合わせて(空気を読んで)しゃべるということがあったかもしれないけれども、詩についてだけは進んで口をつぐみ、誰かとの会話でふと話が詩に近づきそうになったときには、うわべの話をするにとどめるか、じきに別の話題に変えさせてそちらの話題について熱心にしゃべるかした。そうやって周囲を詩から、詩のことが話題となることから遠ざけた。何が起ころうと僕には詩がある、と思えることが何よりも重要だった。 とはいえ僕には、詩は書こうと思って書けるものではなかった(この意味では僕は詩人ではなかったのかもしれない)。そうやって書いたものもないわけではないけれども、そうやってできた詩は自分にとって(そのころの自分にとっても、いまの自分にとっても)あまり意味のあるものではない/なかったように思われる。自分にとって意味がある、あるいは重要だと思える詩は、うまく言えないのだけれども、たいてい「向こう(側)」からやってきたものである。向こうからやってきたものを、ことばとしてキャッチできたとき、あるいはそれがあたかも草木が芽吹くようにおのずとことばや文字となってあらわれたとき、――僕の場合に、ということだけれども――一つの詩ができあがる。自分と「向こう」との境がなくなり、「向こう」と一体になれたとき、僕はたしかに一編の詩を書くことができた。「向こう」からやってきたものが、ことばにならないまま通り過ぎていくこともあるのだけれども、そのなかにも一種の詩的体験はあり、なかにはそれ自身すでに詩と呼べるものが含まれていたのではないかと僕は思う。(ことばで表されたものだけが詩というわけではないのだろう。) 詩を書いた数年間のうち、完全に無職だった期間をのぞけば、少なくとも収入を得るために何らかの仕事には就いていた。そしてそのなかで、多くの社会人と同じように、一週間のうちおよそ5日は職場に通った。休日出勤をすることも多くあった。職場では、通常の業務をこなしつつ、自分に向かって語りかけてくる(投げ出される)「なにものか」を逃すことがないよう、心を集中させた。もちろん集中したところで、「それ」を取り逃がすことはたびたびあったし、「それ」が全く現れてくれないということもしばしばだった。 そうして勤めはじめた職場にも慣れてきたある日、近くの図書館に行く用事があって外出した帰り、しずかな住宅街に迷い込み、歩いているうちに詩興がわいてきたことがあった。町のなかにひっそりと建つちいさな工場(こうば)の中から機械のうごく音やそこで働くひとたちの話し声がかすかに聞こえてきたとき、詩を書かなければ、と僕は思った。 階段の片がわにしろい壁はみえ そのころの僕にとって、詩を書くことは、完全に個人的な営み、自分ひとりだけで完結する行為であり、僕はただひたすら自分、すなわち僕自身のためだけにそれを書いた。そもそも僕ではない誰かのために詩を書くということの意味がわからなかったし、誰かに向けて書かれた時点で(誰か読者を想定した時点で)それは詩ではないとさえ考えていた。 そのころの僕にとって、詩を書くことだけが世界と通じる方法だった。僕にとって、自分が書いた詩だけが世界へとつづく通路だった。詩を書くことをとおして、僕はかろうじて世界の中で立つことができた。息をすることができた。詩とは当時の僕にとって、僕自身のための「聴し」(ゆるし)のようなものだったのかもしれない。僕のなかで、あるいは僕とともに詩と世界とが一つになれたとき、さらには僕と詩と世界が溶け合い混ざり合ったとき、僕は真に生きている心地がするのだった。生を実感できるのだった。本当の生を生きているような気がするのだった。そしてそれは、誰かと共有できる種類のものではない、とそのときの僕にはたしかに思われた。 柴村登治(傍流堂代表)
ちいさくながれる川に
数羽の水鳥はみられ
ふるい窓は木のかげをつくられ
うすぐもりの空はうつる
後ろの室(へや)で
工員たちはひとつのものをつくる作業をしている
建物の入り口へ
ひとの通るみちはせまくつづき
建物のそとへ出ると
べつのひとたちの吐いた息は感じられるようになる
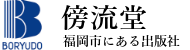

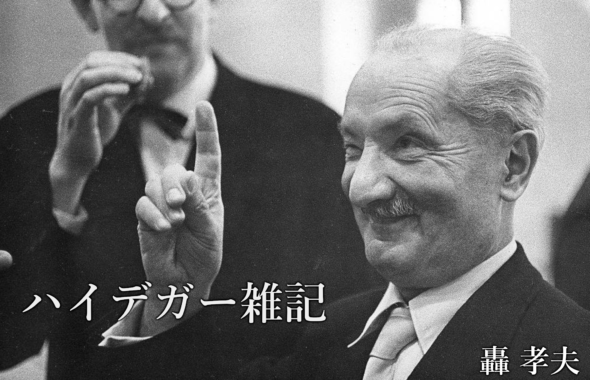


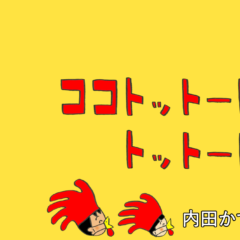


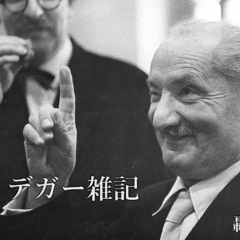
この記事へのコメントはありません。