
第1回 日本古代史の前進のために
邪馬台国は魏志倭人伝に書かれている国名で、奈良説(近畿説)と北部九州説が有力であることは多くの方がご存知だと思います。でも実際に魏志倭人伝を読んだことのある方は多くはないのではないかと思っています。中国の三国時代(魏呉蜀)の歴史を「陳寿」が記した長大な「三国志」のうち、魏志倭人伝は倭国(邪馬台国など)のことが書かれた2000文字に少し足りない漢文です。それでも、朝鮮半島の国々よりはずっと多くの文字数が使われていて、陳寿は倭国を特別視していたように思えます。魏志倭人伝の解釈については、次回から詳しく読み解く予定ですが、今回はまず以下のあらすじをご覧ください。 【 韓国ソウルの北方にある「帯方郡」から「倭国」に行くには、海岸に沿って水行し7000余里で韓国南岸の「狗邪韓国」に到着する。海を渡り1000余里で「対馬国(対馬)」へ、南に海を1000余里で「一大国(壱岐)」へ、海を1000余里で「末盧国(唐津市松浦)」へ到着する。末盧国では潜水して魚や鰒(あわび)を良く捕える。末盧国からさらに東南に陸を500里で「伊都国(糸島)」へ、東南に100里で「奴国(儺(な)、那珂)」へ、東に100里で「不弥国(宇美)」へ到着する。南に水行20日で投馬国へ、南に水行10日、陸行1か月で邪馬台国に到着する。このように女王国より以北の(伊都国や奴国などの)諸国については略載できるが、周辺国である伊邪国、都支国、鬼国、対蘇国、弥奴国、華奴蘇奴国などの状況は良く解らない。また、帯方郡から女王国までの合計は12000余里ある。女王国より以北の伊都国には一大率(いちだいそつ)を常駐させ諸国を監視している。伊都国には世々王がいて、みな女王国に属している。伊都国は帯方郡の郡使が往来する時に常に留まる場所である。また、倭国は海中の洲島を成していて巡り回ると5000余里になる。 倭には牛、馬、虎、豹(ひょう)、羊、鵲(かささぎ)はいない。葬儀に際しては歌舞飲酒(かぶいんしゅ)をする。死者を葬る際の棺(ひつぎ)はあるが槨(かく)は無い。 景初3年(239年)に卑弥呼は官人を魏の都の洛陽へ派遣し、使役人や麻布などを献上した。その返礼として「親魏倭王」金印と、官人用の銀印をもらい、絹織物や刀、銅鏡百枚、真珠などの好い物をもらった。卑弥呼の官人は「文書」で感謝を伝えた。正始4年(243年)にも官人を派遣して使役人や倭錦(わきん:倭国の絹織物)などを魏に献上した。返礼品として官人は印をもらった。 邪馬台国の南には狗奴国(くなこく)があり男子を王としている。官人に狗古智卑狗(くくちひこ)がいる。女王国に属していない。卑弥呼と狗奴国の男王の卑弥弓呼(ひみここ)は不和であり戦争が起こった。戦争の様子を帯方郡に伝えると、帯方郡から張政が倭国に来て黄幢(黄色い軍旗)と檄文により卑弥呼を指導し激励した。正始8年(247年)または翌年(248年)に卑弥呼が亡くなると径百余歩の塚を築いて葬った。卑弥呼の後継者に男王を立てたが国内が収まらず、卑弥呼の同族で13歳の台与(とよ)を女王に立てたら収まった。張政は台与を指導し激励した。台与は官人を魏へ派遣し、使役人や勾玉、倭錦を献上し、その際に張政を帯方郡へ帰還させた。】 申し遅れましたが、私は群馬に生まれ転勤のある仕事に就き、今は退職して東京に住んでいる邪馬台国オタクです。今から30年以上前に、群馬に古墳が多いことに興味を持ち、安本美典氏の『巨大古墳の主がわかった!』(ジック出版局)という小冊子を購入しました。東日本最大の全長210mを誇る群馬太田天神山古墳を、安本氏は崇神(すじん)天皇の子孫である荒田別(あらたわけ)の墓と推定していました。この本に出てくる『奴国の滅亡 邪馬台国に滅ぼされた金印国家』(毎日新聞社)や『季刊邪馬台国』(梓書院)などが気になって次々と買い求め、豊富なデータ提示と理路整然とした安本美典ワールドに魅了されて邪馬台国オタクになりました。 私は転勤で福岡市に2年間住んだことがあります。九州の人は邪馬台国の話題が好きなんだろうなと転勤する前に想像していましたが、意外にもお昼休みの時などに私が言い出さない限りは邪馬台国が話題に上ることはありませんでした。博多出身の人に邪馬台国はどこだと思うか聞いてみても「奈良にあったんやなかと?」と返される始末です。確かにマスコミでは奈良の纏向(まきむく)遺跡が卑弥呼の王宮だと盛んに報道されています。北部九州説は、発掘当初はたくさんの見学客を集めた吉野ケ里遺跡でさえ今では諸説の一つとして付け足しのように扱われているのが現状です。なぜマスコミでは纏向報道が幅を利かせているのでしょうか。それは、近畿を中心とした古墳の発掘で権威になった学者たちが邪馬台国奈良纏向説を主張してマスコミを動かしているからだと私は思います。 関東の友人に「私は邪馬台国オタクだ」と言うと、「意外とロマンがあるねぇ」とか「夢があるねぇ」などと言われます。確かにロマンは感じてはいますが、邪馬台国問題はロマンを遥かに超え、日本の古代史にとって重大な意味を持っているのです。邪馬台国が誕生したのは倭国大乱が収まった180年頃ですから、もし邪馬台国が奈良にあったのなら、九州から近畿まで、ひょっとしたら東日本までを統合する広域国家が180年頃に誕生したことになります。一方、邪馬台国が北部九州にあったのなら、180年頃には出雲や瀬戸内海沿岸、近畿、東海などにも別の勢力が割拠していて、広域国家が誕生するのは奈良に大和朝廷が誕生する280年頃まで待たなくてはなりません。両説には約100年の食い違いがあり、邪馬台国問題を解決しない限り、本当の日本誕生の姿が見えてこないのです。 邪馬台国オタクの私はこの30年間に、北部九州説、奈良説を中心とした諸説に渡る数十冊の先人達の本を読んできました。梓書院の『季刊邪馬台国』は創刊号から最新号の145号まで持っているので(50号までは神田の古書店などで手に入れました)、これらを入れたら200冊以上になります。また、これまで北部九州と近畿のたくさんの弥生遺跡を実際に見てきました。その経験から言うと、「福岡平野にあった奴国を180年頃に支配下に置いて筑紫平野に誕生した邪馬台国は、その後、南部九州へ領土を広げ、280年頃には奈良へも進出して大和朝廷を興し、九州から四国、中国、北陸、近畿、東海、関東に渡る広域国家が誕生した」という、おおむね安本美典説に沿ったシナリオが正しいと思うようになりました。つまり、邪馬台国も大和朝廷も九州の人が興したことになります。このため纏向遺跡の大型建物は、実は初期大和朝廷の王宮と考えた方がいいと思います。それを邪馬台国の王宮と主張するためには、土器も古墳も何もかも、造られた時期を100年古く見積もらなければなりません。そういう無理をして生じた矛盾は全部無視して力説されているのです。奈良纏向説が間違いだとすれば、九州の人は騙され続けてきたことになるので怒らなくてはいけません。九州の人だけでなく間違った日本史を信じ込まされてきた日本人全員が怒らなければなりません。 古代史に何の権威もない単なる邪馬台国オタクの私がここまで断言するのは、産能大学名誉教授の安本美典氏の総合的な膨大な分析をはじめ、三角縁神獣鏡は後漢式鏡ではなく国産であると初めて主張した同志社大学名誉教授の森浩一氏、鏡や鉄などの出土品の詳細なデータを明らかにした元宮崎公立大学教授の奥野正男氏、遺跡から出土する絹製品を鑑定した京都工芸繊維大学名誉教授の布目順郎氏、高地性集落の研究を行った山口大学名誉教授の小野忠熈氏、鉛同位体比で銅製品を分類した元東京国立文化財研究所の馬淵久夫氏、土器の編年から卑弥呼の墓と宣伝されている箸墓古墳の築造年代は4世紀中頃(350年前後で卑弥呼の死後100年ほど後)だろうと分析した元橿原考古学研究所の関川尚功(ひさよし)氏などの先人が探求した膨大なデータと考察結果が本となって私の手元にあるからです。 この連載は新説や奇説を打ち出して注目を集めようとするものではありません。これまで先人が切り開いてきた邪馬台国問題の妥当な解決策を取り入れて、私なりに合理的にまとめる試みです。邪馬台国問題の原点である魏志倭人伝に添って、邪馬台国時代の出土品を証拠として、次回から詳しくお話ししたいと思います。その後、邪馬台国の後継勢力である大和朝廷が編纂した「古事記」(記)と「日本書紀」(紀)の真実にも迫っていきます。記紀神話は決して作り話やおとぎ話ではないことも先人が教えてくれました。 「九州人が邪馬台国と大和朝廷を興した」がこの連載のタイトルです。この連載は推理小説で言えば一番おもしろいラストの謎解きに当たります。これまで謎だと思われていた伏線がすべてつながって、確かにこの結論しかありえない、という納得感を皆さんに味わっていただきたいと思います。多くの先人の努力により邪馬台国問題はもう解決していると思います。本当の日本建国史を知る喜びを一緒に祝い、日本古代史を前進させることを目指します。よろしくお付き合いをお願いします。 高橋 永寿(たかはし えいじゅ) 1953年群馬県前橋市生まれ。東京都在住。気象大学校卒業後、日本各地の気象台や気象衛星センターなどに勤務。2004年4月から2年間は福岡管区気象台予報課長。休日には対馬や壱岐を含め、九州各地の邪馬台国時代の遺跡を巡った。2005年3月20日には福岡県西方沖地震に遭遇。2014年甲府地方気象台長で定年退職。邪馬台国の会会員。梓書院の『季刊邪馬台国』87号、89号などに「私の邪馬台国論」掲載。
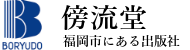


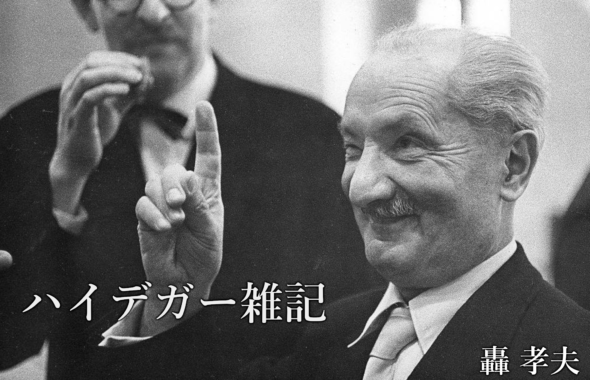


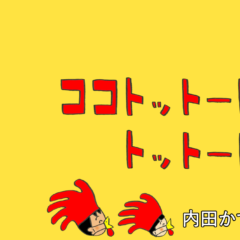

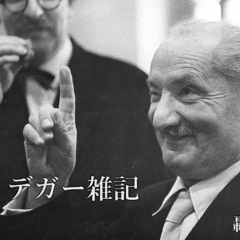
高橋様
九州邪馬台国説に賛成です。
卑弥呼も天体観測オタク・稲作オタク・養蚕オタクで日本全国にこれを広めようとしたのではないか?
私は卑弥呼が西の端にいなければならない理由があると思っています。
それは春分・秋分の日に重点を置いて日昇を観測して各種農事、特に重要なのは稲作のタイミングを読んで作付けの号令をかける事ではなかったかと。
作付けの号令を列島西端の九州北部平野からだとただ1回号令をかけるだけで桜前線が上るように西から東へ稲作前線を上らせることが出来ますが、奈良盆地からでは西側が手遅れになり不可能です。
例え海峡などで隔てられても狼煙などで弥生時代でも十分可能だと思います。
ただ集落から集落へ伝播させるだけです。
もう一つ、先般話題になった吉野ヶ里遺跡石棺墓ですが、その石蓋の形態が蚕の蛹に似ています。
そうすると、その下の石棺が異常に細長い理由が蚕の幼虫を表現しているのではないかと。
そういえば蚕は天の虫と書きます。実際の蚕は家畜化され飛べませんが、この弥生人の魂は天空星空の世界に運んでくれたようです。ただし、甕棺墓に埋葬された人々は永遠に繭に閉じ込められたままですが。