
第6回 丹後へ
写真家、畠山直哉との出会いは大学時代であった。当時、仲良くさせていただいた中倉さんが彼の評論を文芸部の冊子に書いていたのだ。中倉さんとは、自分のことを「ズボら」と称していたようにちょっと浮世離れしていながらも現代アートと中上健次をこよなく愛する一つ上の先輩であり、ぽっちゃりめの頬と真っ黒で真っすぐな髪が特徴的。これらは人によってはチャームポイントとなり得るか。何はともあれ、いつも古びたパタゴニアを着て(文芸部の人は押し並べて小奇麗だった)、大学構内を走り回り(当時からランニングが趣味だった)、家が遠いからと嘯いて1週間くらい部室に泊まり込み(うざい、くさい)、ふと気が付けばしばらく姿を見せない(頻繁に旅に行っていた)僕に対して、異分子扱いせず、汚い人を見るような視線も投げ掛けず、たまに都内まで一緒に映画を見に行き、フランス文学科の単位習得が危うくなるや、出来る範囲の手伝いをしてくれた優しき女の子であった。 我らの在学中に、畠山の「ライム・ワークス」が第22回木村伊兵衛写真賞を受賞。それを受けての執筆だったよう。彼の名が全国区になりつつあったし、写真に関しては今も昔も縁遠い僕であるが、中倉さんとの話のタネになるかと思い、その評論を読んだあとで畠山の写真を見てみれば、その独特な色合いに目を惹かれた記憶がある。そもそも石灰石の鉱山や工場などをよくよく見たことはなかったが、そんな過去の遺物になりかけている一帯にも、あまりにも非自然的な構造物にも、確かな美が秘められているということか。とかく大学時代は友人からの情報収集ほど手っ取り早く、かつ有意義なものはなかった。 最終学年まで80単位を残しながらも奇跡的に大学を卒業し、ついぞ恋愛関係に発展することがなかった中倉さんと音信不通になってからも時折、彼の写真展に足を踏み入れ、そして我が家の本棚には今もって彼の重要作、『陸前高田 2011-2014』(河出書房新社、2015年)が礼儀正しく飾られてある。もっとも、僕がことさら感銘を受けたのが『気仙川』(河出書房新社、2012年)。故郷を襲った震災を巡る旅の記録だ。2011年3月11日、東京で生活をしていた畠山には現地の情報が、親族家族の安否がまるで伝わってこない。いつまでたっても連絡は途絶えたまま。現代日本人にとって未曾有の事態。ここにとどまれと脳内は訴えてくるが、肉体はじっとしていられない。元来が論より証拠の性格。愛用のバイクに飛び乗り、分断、破壊された道路を迂回しながら、数日かけて陸前高田へ徐々に近づいていく。憂慮、憤懣、疑念、焦燥、絶望、貧窮…負の感情しか湧き出てこない日々。もちろん、これは写真集との分類だろうが、(僕にとっては)震災前後の陸前高田の写真よりも文字のほうにグッときた。これほどまで緊迫感と迫真性のあるエッセイはそうはあるまい。真実以上の真実がそこにあった。 『写真と文学 何がイメージの価値を決めるのか』(塚本昌則編著、平凡社、2013年)に寄稿した管啓次郎が「この本に一回限りの高貴さを与えている」理由を、詩人ならではの筆致で説明している。まず管は「写真とは、目をつぶってたたずむ経験に非常に似ている」と呟く。シャッターが切られた瞬間に現実からの隔たりを受け、他の場所、未来のある時間への移行可能性が生起し、その画像は眼前から失われた対象を心に思い描くもの、心象へと移行していく。その時系列をもたない心象世界では「そこにはない過去がまざまざとよみがえり、空想しただけの場面が現実とまったくおなじ強さをもって存在を主張し、証拠写真をもつかもたないかだけが現実世界と可能世界を分ける基準となって、この基準としての価値によって写真の地位が他ではありえないかたちで高められる」。それが他ならぬ『気仙川』であり、さらに核心をつけば「破壊の前/後という写真世界内部の対立のみならず、いわばそれと直角に交叉したかたちで、写真世界と心象世界のきびしい葛藤が同時にある」。尋常ならざる緊張度の高さ。それを「高貴」と呼ばずして何と呼ぼう。 * * * 二条駅から特急はしだて3号に乗って、大江駅へ向かう。パタゴニアのリュックの中に『丹後 古代史の遠いこだま』(池澤夏樹著、畠山直哉写真、河出書房新社、2024年)を忍ばせて。乗車率は70%くらいか。今回のBGMはおばちゃんではなくおじちゃんの一行だ。新幹線やボックスシートに座ると、一杯やりたくなるのは日本人のDNAか。ゆらりゆられて仲間と楽しい宴。我々は二人静かに旅程の相談。今日の今日まで判断保留としてきたのだ。この前の伊勢よろしく、丹後には厚い雲が垂れ込めているようだし、晴れか雨か、傘が必要か否か、使える交通手段は何か、行ってみないことには分からなかったのだから。 今回は、元伊勢内宮皇大神社と元伊勢外宮豊受大神社が主たるターゲット。伊勢の伊勢神宮2社と同じく、こちらもやや離れたところに位置している。この点も旅程を少し難しくしている理由なのだが、考え得る選択肢は3つだ。 プランA(タクシー)…大江駅→外宮→内宮→宮津駅 これは雨の日バージョン。徒歩、自転車では難儀となるため、タクシーで2つの神社を回って、10キロ先にある宮津駅まで一気に行ってもらう。この駅からなら宿の送迎車が待ってくれている網野駅まであとわずかだ。少々お金は張るが、疲労度は極めて低く、短時間で行ける利点がある。残念な点は丹後の自然(=丹後天橋立大江山国定公園)を楽しめることができないこと。そして風情がないことか。 プランB(徒歩)…初日、大江高校駅→外宮→大江高校駅→網野駅 二日目、網野駅→大江山口内宮駅→内宮→大江山口内宮駅 最も実現可能性が高いと考えていた。1つの神社に一日を掛ける贅沢プランとも言えようか。これならたとえ雨降りでも時間はたっぷりあるので実現可能だ。その反面、翌日は宿周辺の探索に時間を掛けられない上、雨降りなら傘の購入が欠かせず、シューズも汚れてしまう。ちなみに、大江高校駅は大江駅の一つ先、大江山口内宮駅はそこから3つ先の駅。 プランC(自転車)…大江駅→外宮→内宮→大江駅 事前に問い合わせをしておらず、大江駅に自転車のレンタル会社が存在しているのか不透明であったが、最も時間的、労力的に都合が良いので無責任ながらもプランとして立てておいた。それこそ雨降りでなければ交通費は安く、それなりに周辺の自然観察も可能で、かつ風情もなくはなく、翌日は丹後の海をじっくりと見ることができる。 * * * 恐る恐る大江駅に降りてみる。この時、雨はやんでいた。結構、大きな駅と踏んでいたが(特急の停車駅だから)、改札口には誰もおらず、その脇に小さなメタル色の箱が。「切符はここに入れてください」と書いてある。書いてあるから切符を押し込んで無人改札口を通り過ぎてみれば、「こちらに切符を渡してください」との金切り声が横から飛び込んできた。その発声源に目をやると(事務所みたいな空間だった)、30手前くらいの女性が怖い顔をして立っている。なにか、間違ったことをしでかしてしまったのか、我らは。「いや、そこの箱に入れてしまったんですが」「ああ、そうですか。それならお通りください」。つっけんどんな物言いにちょっと気分を害したが、厳しい検問をクリアできたような安堵感も生じ(なんか理不尽だが)外へ出てみた。タクシー1台すら見当たらない寂しい広場に面くらったが、エントランス脇にレンタサイクルとおぼしき自転車が数台置かれてあったのを確認するや、今度はまっとうな安堵感に包まれた。いやしかし、どこに行けば手続きできるのだろうか。まさかさっきの女性に聞くしかないのか。嫌な気持ちを抑えつつ、再び突撃すれば「それじゃあ、ここに書いてください」と同じ口調で指示してきた。今日はきっと、通勤中にすっころんで腰を強く打ち付けてしまったのだろう。こちらは無心でテキパキと名前や電話番号を書き込み、思いのほか、ちゃんと注油をされて漕ぎやすい自転車に跨り、颯爽と京都府道9号綾部大江宮津線を北上したのである。 山間の低地を流れる宮川と併走する形で道路があり、車もさることながら人も滅多に出くわさない。出くわすとすれば、下校中の中学生チャリ部隊だけ。でも、土地柄か、スピードはひどくのろい。こちらは別段、急ぐ必要はないものの、一応は1時間半で大江駅に戻らないと、網野駅での宿の送迎バスが出発する時刻(=15時30分)直前に到着する電車に間に合わない。そんな事情もあった。11月下旬、さすがにひんやりとし過ぎてはいたが、清潔感ある空気は極めて心地良く、せっせとペダルを回して、とっととチャリ部隊を抜き去り、10分と少しで外宮に到着した。 かなり幅のある石段がずっと上方まで続いている。えっさえっさと足を運ぶ。神社前の広場に来ても猫一匹いない。さほど広くない境内。前方にはお馴染み、神明造りの本殿がある。伊勢神宮の20年ではなく、こちらは60年周期で式年遷宮が行われていたというがしかし、現在の本殿は明治7年(1874年)の造替であり、やはりと言うべきか、周りの土宮、多賀宮、月宮、風宮、そして卸幸神社すべて年季が入っている。本殿の後方にそびえたつ「龍燈の杉」は見事であったが(太宰府天満宮の樟がまさにそうだが、とんでもない大木に出会えるのは寺社巡りの醍醐味)、全体的にかろうじて伊勢神話の面目を保っている状況だ。 次は内宮。風を切って走る。宮川を渡り、左側に延びている細い道に入る。ここが参道ということは、両脇に連なる宿、食事処、土産物屋――すでにひとけはない――から窺い知れる。じきに前方に石段が現れ、もはや自転車はここまで。再び、いや、一層過酷な筋トレが開始されたのである。 神護寺さながらのきつい石段を上り切ると、外宮ほど陰気な雰囲気はなく、ちらほらと参拝者の姿も。本殿は平成22年(2010年)に改修されたというが、ここにも「龍灯の杉」が。推定樹齢2000年。もっとも、石段の途中にあった「麻呂子杉」のほうが圧巻だったか。天まで真っすぐ伸びている1本の太い棒。何はともあれ、宮川のほとりに佇む外宮とは違い、内宮は大原生林の一角であるためか、神秘性は確かに感じられ、かつて年間に8万人もの参拝者が存在したのも頷ける。周辺も散策したい気持ちはやまやまだったが、時間的猶予があまりなく、急ぎ足で大江駅に戻った次第である。 丹後鉄道の多くの駅は切符の自動販売機は置いておらず、大江駅も例に漏れない。またもや〝あの人〟に出くわすのかと緊張感に包まれたが、新卒といった感じの若い女性に入れ替わっていたのでほっと一安心。楽な気持ちで網野駅までの切符を催促すると、〝あの人〟に輪をかけて棘のある言い方で対応してくるのだから唖然茫然である。この人も通勤中にすっころんでしまったのか。それとも、無愛想は丹後という土地特有の現象なのか。それならそれで合点がいく。こちらに落ち度がなければ構わない、仕方がない。ちょっと驚いたけど。 宮津駅で方向転換し、宮福線から宮豊線に入る。丹後の海が見える、天橋立も見える。十数年ぶりの光景とはいえ、まったく変わらない。網野駅からは約30分、バスに揺られて今日の宿、間人(たいざ)温泉「炭平」に到着した。台風が通り過ぎた直後だったゆえか、丹後の海はあくまで荒々しく、波音はあまりにも轟々しい。かつて大陸から命からがらに漂流してきた者に映る丹後の風景は、決して心和むものではなかったであろう。 * * * 夜は待ってましたの蟹料理。優しい甘みたっぷりの刺身も悪くないが、しゃぶしゃぶが絶品。口に入れる前に肝を付けるのがキモ。たらば蟹はこの食べ方が一番だ。刺身よりも遥かに旨味が感じられるし、これほどまで新鮮な肝は遠方たる都会ではなかなかありつけまい。途中、担当とは違う仲居さんが現れ、記念にどうですかとカメラを掲げてパシャリ。今はやりの旅館は、なかなかオツなサービスをするものだ。 このあと、床に就くまでの時間は『丹後』で。先月、妻が「丹後」の一語を発したときから畠山直哉と池澤夏樹とのコラボ作品が気になって仕方がなかった。この二人、僕にとっては長らく重要人物であったが、まさか、深い親交があったとは。出版された当時、買おうか買わないか迷って結局、手に取らなかったのだが、こんなにも早く出会えるとは思わなかった。これも何かの縁。行きの電車では畠山の写真を堪能したので今は池澤による詩を。それは古代史の遠いこだま… この先に陸地はあるのか 無限とか永遠とか… 無為のまま果てのない歳月とか そして深夜の賑やかな星たち 目を凝らす先、海と空の間に黒い線が見えた 近づくと手前の森の濃い緑と奥の柔らかな山並みに分かれた ここだ、とうすよごれた男が初めて口をきいた しかしこの海岸には浜がない あの木々の一本に見張りがいる、とうすよごれた男は言った 常に常に海を見ている やがて迎えが来る (出典 『丹後 古代史の遠いこだま』) * * * 翌朝も風は強く、むしろ波濤は激しさを増していた。豪勢な朝ご飯を食べたあと、「山陰海岸ジオパーク」と呼ばれる海辺沿いを歩き、2キロほど北にある「立岩」という名所まで行ってみることに。道路が濡れている。ここまで波が押し寄せてきたということか。いまも、水しぶきが時おり、頬をなでる。連れはおっかなびっくりしながら歩を進めていたが、その名の通り小ぶりの小間漁港を、青年の佇まいを見せる間人漁港(昨晩の蟹はきっと、ここに揚がったのだろう)を横切り、小高い水無月神社に到着。神社といっても鳥居はなく、人間の背丈よりも少し高いくらいの社があるだけだ。ここからの眺めが良い「立岩」…エアーズロックを彷彿させる高さ20mの一枚岩は荒ぶる丹後の象徴的存在だろう。しかしここも風が強い。体が冷えに冷える。一時避難するべく、少し内陸にある道の駅「てんきてんき」に移動した。土産物や地元野菜をゆっくりと眺めたあと、丹後の塩を使用した塩バニラソフトを購入。少し体が暖まったことだし、外に出て食べることにした。 「ちょっと、気を付けてよ」 「なにが」 「とんびが飛んでいる」 「それがどうしたの」 「狙っているわよ」 「大丈夫だよ」 「早く食べたほうがいいと思う」 「ゆっくり食べようよ」 と、言った矢先、右からシュンと一陣の風がやってきたかと思えば、手元のソフトクリームが一瞬にして消えた。まるで手品のように。 「ほら」 「びっくり」 「だから言ったでしょ」 それにしてもだ。僕の手に触れることなく獲物だけかっぱらっていくのだから素晴らしき運動神経だ。人への優しさ、配慮がある。もしかすると、世界一級のサーカスに入団できるかもしれない。電信柱のてっぺんでモグモグしているが、こんな甘いものも好きなのか。まだ三分の一くらいは残っていたので名残惜しい気持ちはあったが、天晴れな敵との遭遇に何ら遺恨はなかった。 近くのバス停でひと息付いているときから何かこう、胸のあたりがモヤモヤとし始めてきた。強烈な潮風をあたり続けたのが良くなかったか。バスの中では目をつぶり、休息に努めることに。目を覚ますと網野駅が目前であったが、一つ先の峰山駅まで行けるというので、そのまま乗り続けた。電車やバスの時間をあれこれ熟慮していると、うまくいけば峰山駅からほど近い金刀比羅神社に参拝できるよう。失敗すれば大変なことになるが(まあ、帰宅時間が4時半から6時になる程度だが)、この「丹後のこんぴらさん」は狛犬ならぬ狛猫がたくさんいるようだし(妻は大の猫好き)、ここでお参りすれば無事に帰宅の途につけるという話だ。それなら行くしかない。行ったほうが安全。またもや急な石段を上ることになったが、しっかりと参拝して峰山駅へ。 切符売り場で50代と思しき男性職員に「二条までの特急券が欲しいのですが」と丁重に求めたら、「時間がないから特急券は天橋立で買って。そこまでの切符は出すから」と意味不明な返答が。例のごとく、ぶっきらぼうな口調で。ここで特急券が買えない理由が分からないし(機械の故障?)、そもそも「時間がない」はどういうことか。発車まで5分以上はあった。それとも実は目下、彼は大量の仕事を抱えているのか。早く特急券を買わないと指定席が売り切れてしまう可能性があるんですけど…。やはり丹後は、容易には来訪者を寄せ付けない場所なのだ。 それでも天橋立駅で無事に特急券を購入することができ、定刻通りに京都へ走り出した。その車内。昨晩の写真を取り出し、改めて見つめていると、はたと気付いた。50を過ぎた自分の風貌は祖父に似始めているということだ。かどばった輪郭、たれ気味の目じり、頬のしわ加減。小さい頃は母似と言われていたが、いまや完全に父の方…虎石家のほうだ。もともとは新潟の寺の住職の家系。高祖父が家を出て、大きく二手に分かれたという。いまもあるのかその寺は。にわかに自分のルーツが気になりだした旅の終わりである。 虎石 晃 1974年1月8日生まれ。東京都立大学卒業後は塾講師、雑誌編集を経てデイリースポーツ、東京スポーツで競馬記者を勤める。テレビ東京系列「ウイニング競馬」で15年、解説を担当。著書2冊を刊行。2024年春、四半世紀、取材に通った美浦トレーニングセンターに別れを告げ、思索巡りの拠点を京都に。趣味は読書とランニング。
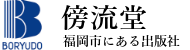


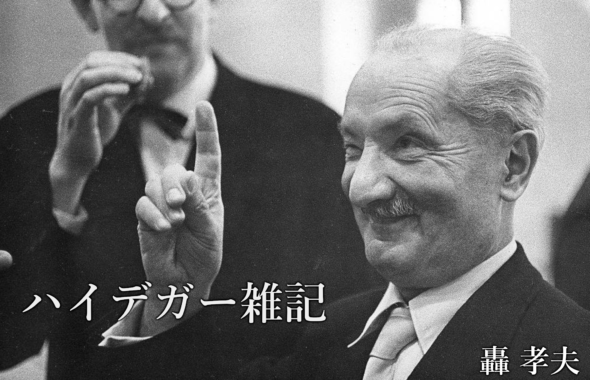

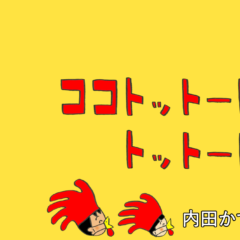


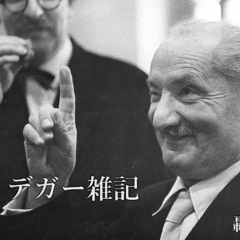
この記事へのコメントはありません。